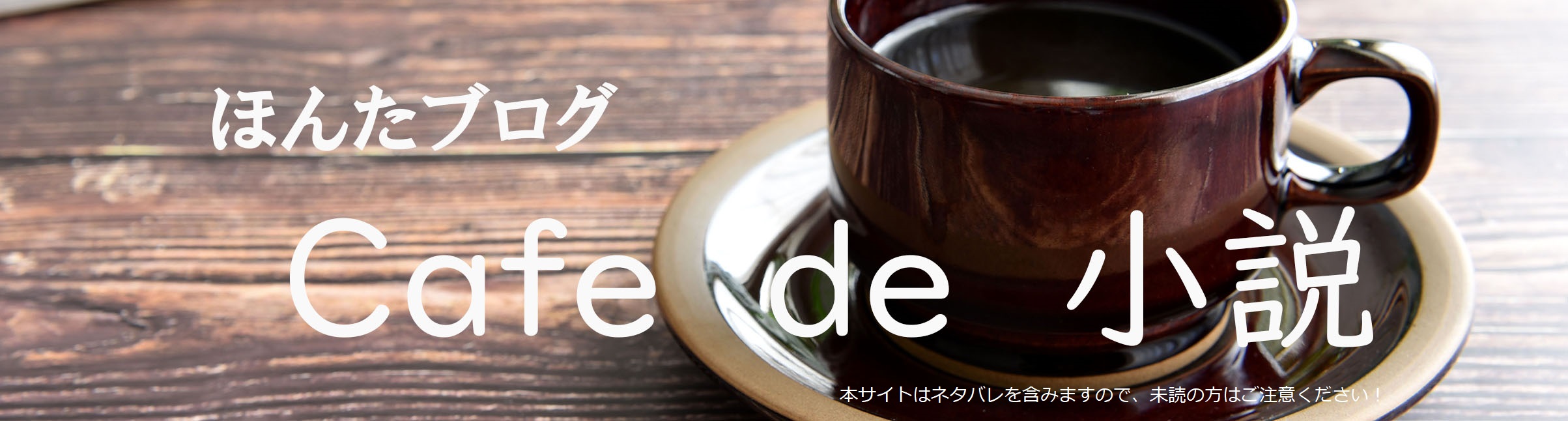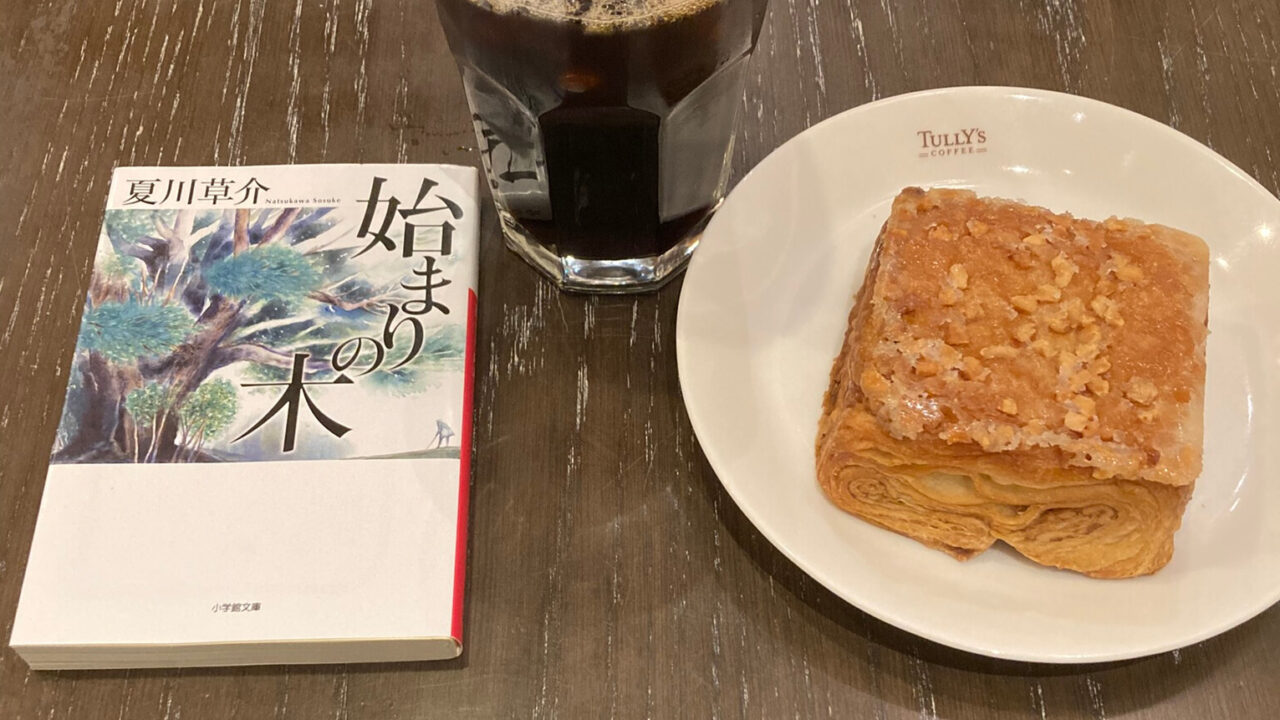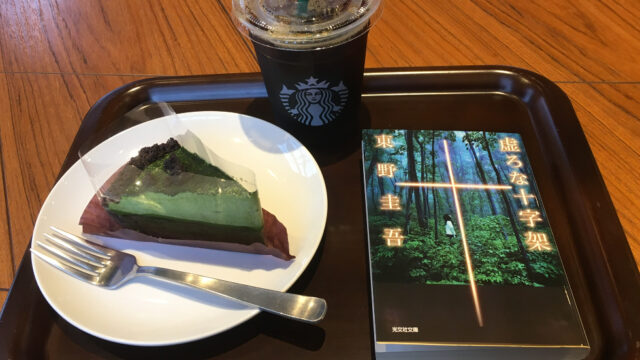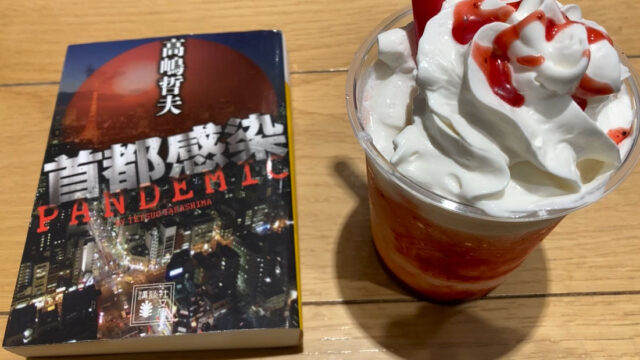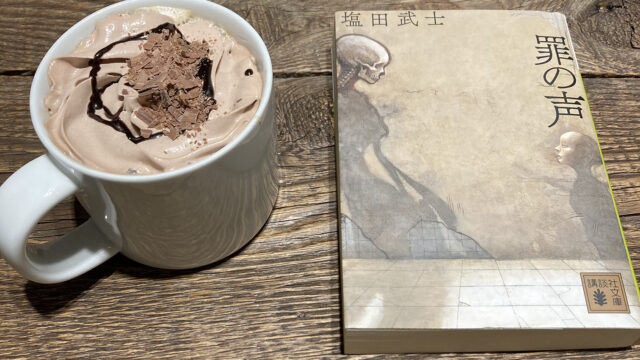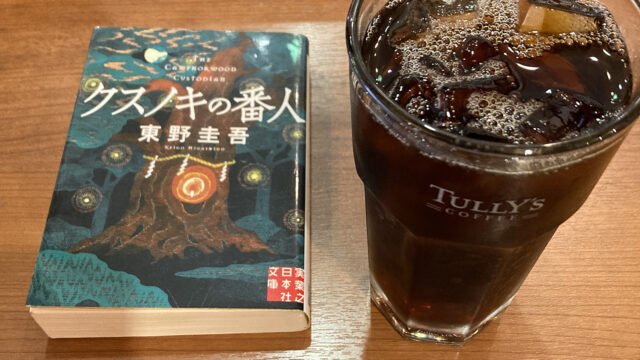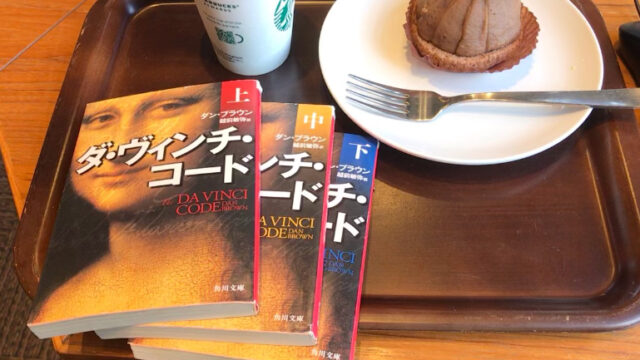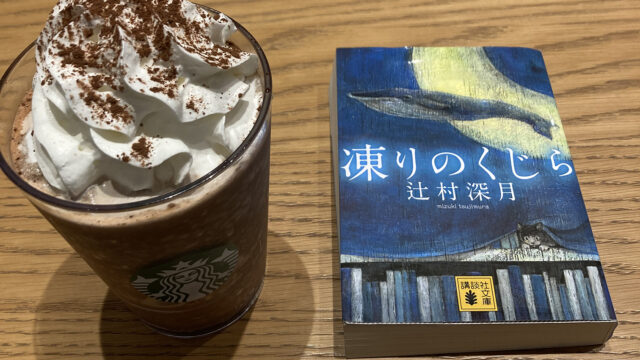夏川草介先生の作品。夏川先生の作品はこれまで「神様のカルテ」「本を守ろうとする猫の話」など,いくつかは読んできました。
夏川先生は信州大学の医学部を卒業され,現役の医師であります。
神様のカルテのような医学をテーマにした作品もありますが,「本を守ろうとする。。。」という作品のように医学以外のストーリーも描かれる方です。
現役の医師なので,とても忙しい傍ら小説を描かれているのかなって思います。知念実希人先生や,中山祐次郎先生などのように。本当にすごいと思います。
今回の「始まりの木」は「民俗学」という学問をテーマにした作品です。
民俗学というものがどんなものであるか,その学問を学ぶ目的とは何なのかに興味がある方は,是非読んでほしいと思います。
目 次
1. こんな方にオススメ
2. 登場人物
3. 本作品 3つのポイント
3.1 民俗学とは
3.2 民俗学の神髄と衰退
3.3 本作品の考察
4. この作品で学べたこと
● 民俗学というものが何かを知りたい方
● 民俗学を学ぶ意味を知りたい方
神様を探す二人の旅が始まる。「少しばかり不思議な話を書きました。木と森と、空と大地と、ヒトの心の物語です」
-夏川草介-
藤崎千佳は、東京にある国立東々大学の学生である。所属は文学部で、専攻は民俗学。指導教官である古屋神寺郎は、足が悪いことをものともせず日本国中にフィールドワークへ出かける、偏屈で優秀な民俗学者だ。古屋は北から南へ練り歩くフィールドワークを通して、“現代日本人の失ったもの”を藤崎に問いかけてゆく。学問と旅をめぐる不思議な冒険が始まる。
“藤崎、旅の準備をしたまえ”
Booksデータベースより-
1⃣ 民俗学とは
2⃣ 民俗学の神髄と衰退
3⃣ 本作品の考察
主人公は藤崎千佳という,東々(とうとう)大学の修士課程で民俗学を専攻する学生です。
民俗学? 何か古い時代のことを研究しているようなんですけど,そもそもこの民俗学ってどんな学問なんでしょうか。古いと言えば考古学を思い出しますけど,それとはどう違うのでしょうか。
民俗学と考古学の違い
考古学と民俗学というのは、どちらもいわゆる「歴史学」の一分野です。
考古学は土の中に埋もれていた遺物や遺跡を研究対象にして、そこから歴史を再構築するもの。
それに対して民俗学は、人々の間で、特に口で伝えられてきた“伝承”をもとに歴史を再構築する学問です。
さらに古文書など昔の文献をもとに歴史を明らかにする文献史学の三つをあわせて、広い意味での歴史学となるわけです。
-神奈川大学サイトより-
なるほど,両方とも歴史を知るという意味では同じような学問だけど,そのアプローチの仕方が違うというわけなんですね。
ここで民俗学を教える古屋という先生が登場します。この古屋はとても頑固で堅物で偏屈な人物のようです。そんな古屋の元で学ぶのが千佳というわけです。
古屋の講義に出席する学生はいますが,古屋自身が出席も取らないし,自分の授業に集中しすぎているのか,学スマホをいじったり,他のことしながら授業を聞いていたりしているんですね。
昔,学生時代にそんな感じで授業を受けていた自分のことを思い出してしまいます。今では後悔してますけど。。。
古屋のゼミには千佳と,博士課程に在籍している仁先輩こと,仁藤仁の二人しかいません。それでゼミが成り立つのか。それとも民俗学自体を研究する人が圧倒的に少ないのだろうか。ちょっと興味が湧いてきました。
古屋は全国のいろいろな場所へ足を運びます。本作品でも青森,長野,京都,高知,そして舞台となっている東京などの由緒ある場所へ行って,いろいろな人と出会って話を聞いたり,その場所に伝えられていることを学んでいくのです。
そこに必ずついていくのが千佳でした。なぜこんなに全国各地を,しかも飛行機などに乗らずに列車で移動していくのか。ただ単に荷物持ちのようなふうにも思えますが,何か古屋は千佳に何かを伝えたいようにも思えます。それがここではわからない。
まるで「民俗学の神髄に自分の力で気づけ」と言われているようにも思えます。
大学のゼミに在籍しながら,全国各地を廻って研究するというのが古屋のスタンスなのです。
千佳は,なぜ古屋が「民俗学を研究しているのか」ということに辿り着くことができるのかというのが一つの大きなポイントのようです。
旅の途中,というか研究の一環で京都を訪れた際,千佳と古屋はある少年に出会います。その少年は絵を描くのが好きなようで,京都の紅葉を描こうとしていました。
その少年と別れた後,ある二人の男女と出会います。それはその少年の両親でした。ところがそこで驚くことを聞きます。実は絵描きの少年は,すでに一年前に亡くなっているというのです。
しかし,古屋は気づいていました。そして千佳にこういうのです。
「かつて行きたかった場所があった,この世にいないはずの人間が,初めての命日に一度だけその場所行けることがある」
これもこの土地で伝えられた話でした。いろいろな場面で,古屋は千佳に伝えます。
○ 人生の岐路に立たされた時,民俗学の知識が役に立つことがある
○ かつてはこの国には無数の神がいた。その土地で人間を見守る存在だった。
○ 日々のことを記録し,その記録はどこかの研究者が役立ててくれるだろうと思ったこと
が,民俗学自体が考古学や文化人類学に侵食されてきた理由だ
なんだろう。民俗学の神髄がここに隠れているようなするセリフです。
千佳自身も古屋と行動を共にするようになり,何かを感じ始めているようにも思いました。
私たちが目にする昔からある大木一つにしても,昔の人々はそこに何かを見出そうとした。それが日本にとっては神のことなのではないか。
神様がいるということは,そこに目に見えないものが感じることと同じことであると。
ある住職も「君の心の中に仏様はいるかい?」と問います。
神や仏。神棚や仏壇。神教や仏教。日本では他の宗教とは異なり,戒律の厳しい宗教は持っていないように思います。それは信じることではなく,感じることが重要なのだと本作品では言っています。
分かるようなわからないような。でも何か的を射ているような気もします。
この分かりにくさや曖昧さというものや,昔からあるものどんどん排除し,新しいものに変化させてきたことが民俗学の衰退に繋がっていったのでしょうか。
そんな千佳たちが在籍している民俗学講座も廃止になるという状況になってしまいます。さすがに学生が2名しかいないゼミを存続させるのは難しいのか。
このピンチに,古屋や千佳がどういう行動にでるのか。誰かがこのピンチを救ってくれるのでしょうか。
このピンチを乗り越えられるのか。この後は実際に本作品を読んでほしいと思います。
僕自身はうちに神棚がある家で育ちました。その時はどの家にもこういう先祖を祀ったものが置いてあるものだと思ってました。
でも友人の家に行けば,どちらかというと仏壇がある家が多かったりして,一体何が違うんだろうって思ったことがあります。
歴史を学ぶようになり,その原点の違い,信仰の仕方の違いなどを感じるようになりました。でも疑問もありました。なぜ初詣には宗教関係なく,神社へ行ったり,お寺へ行ったりとするんだろうと。
人それぞれ何かを考え「目に見えないもの」に対して感謝をしたり,願ったりすることを考えながら日本人は生きているのかなって思いました。
もちろん願えば叶うわけではない。合格祈願でさえ,うまくいかないことがある。
僕自身も「苦しい時の神頼み」みたいなものを何度もした経験があります。でも年齢を重ねるにつれ,神棚に向かって,今生きていることに感謝することが多くなりました。
良いことがあればもちろんですが,良くないことがあったとしても「これは試練を与えてくださったのだ」と感謝しています。
普段生活している中でも,不思議と何かに護られていると感じることがあります。
過去には自転車に乗っていて,交差点の真ん中まで車に撥ね飛ばされるという大きな交通事故に遭ったこともありました。
全部僕自身の過失だったのですが,運よく打撲で済みました。一歩間違えれば命もなかったかもしれない中,生きていられたのは「これを教訓に生きていけ」と言われているようにも思いました。もちろんその言葉の主の姿は見えません。
あの時,この世には説明できない,目に見えない何かがあるのかなって思った記憶があります。
本作品を読めてよかったです。
とても考えさせられる作品だと思うので,是非読んでみてください!
● 民俗学というものがどんな学問なのかを知ることができた
● この世には理屈では説明できないものがあるということ
● これからも生きていることに感謝したい