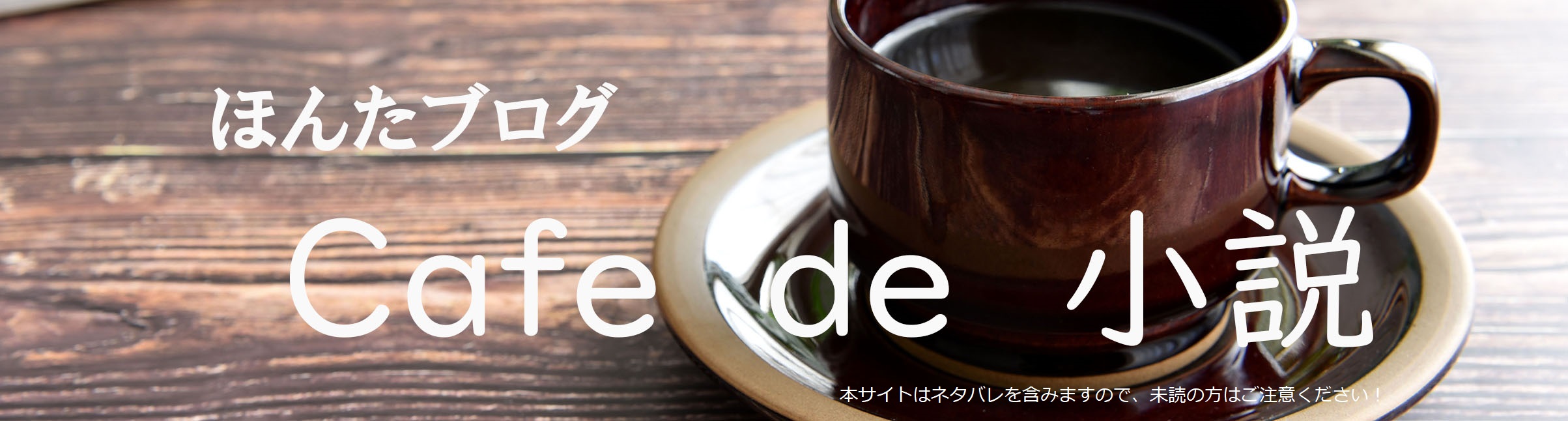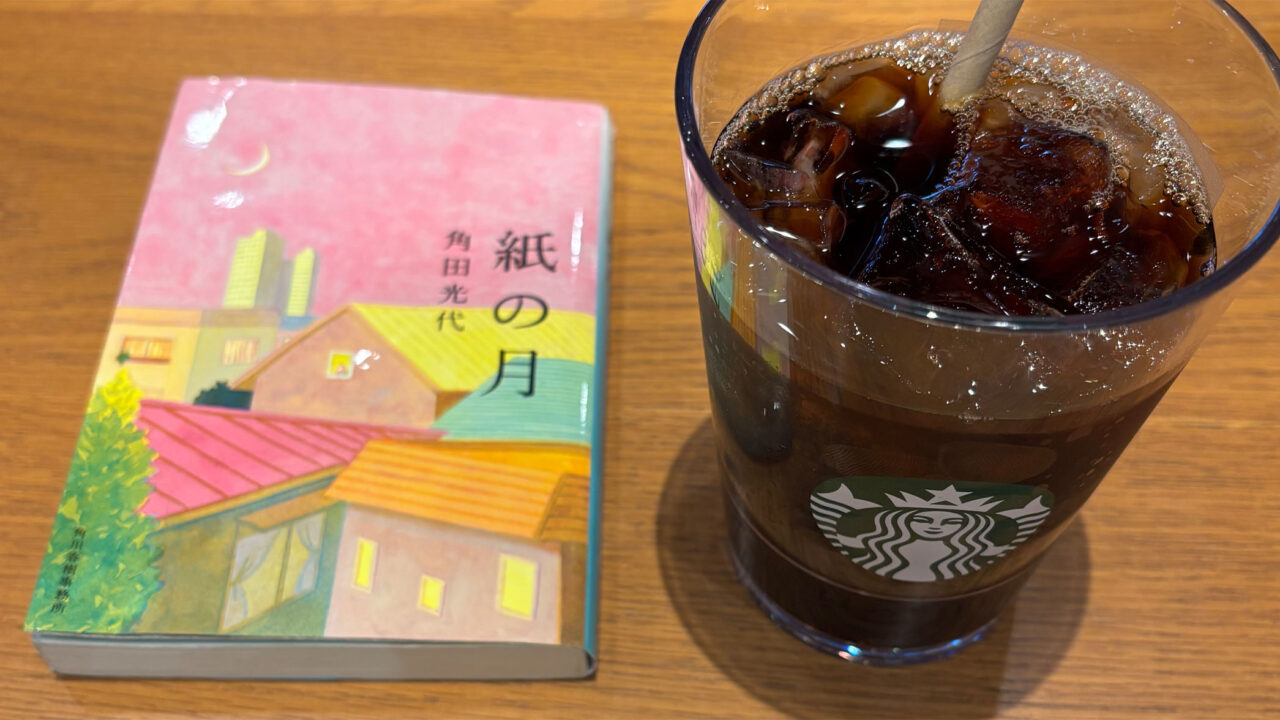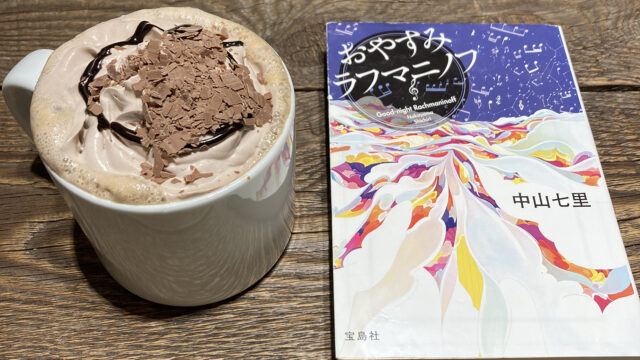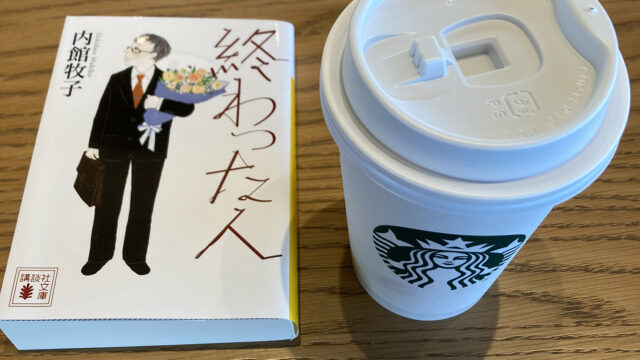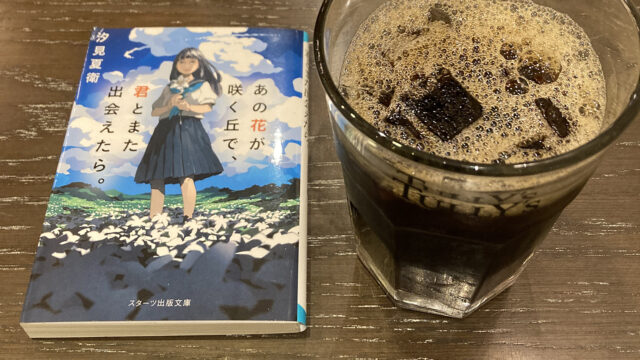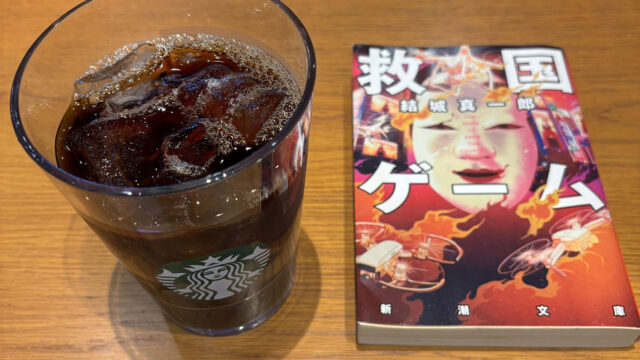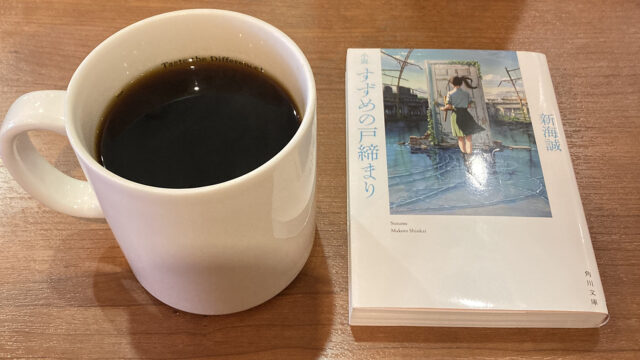「銀行員,一億円横領事件」
パートだった銀行員が,どういう経緯でこの「犯罪」を犯してしまったのか,というのが本作品のテーマです。
横領というのはそんな簡単にできるものなのだろうか。それを知りたくて本作品を手に取りました。
読んでいけばわかりますが,この女性銀行員にそんなつもりはなかった。しかし,小さな過ちが徐々に膨らんでいって,気が付いたらとんでもないことになっていたということなのだと思います。
2012年に発刊され「柴田錬三郎賞」を受賞し,2014年にはドラマ化,映画化されています。その女性銀行員は,ドラマ版は原田知世さん,映画版は宮沢りえさんです。
詐欺の進展とともにどんどん読み進めていくスピード感。
そして,すでに海外に逃亡しているこの女性に,警察はどうやって行きつくのか。
ハラハラしながら読める作品です。是非,読んでみてください!
目 次
1. こんな方にオススメ
2. 登場人物
3. 本作品 3つのポイント
3.1 梨花に対する印象
3.2 横領に手を染める梨花
3.3 梨花の逃亡
4. この作品で学べたこと
● 主人公が横領事件とはどんなものなのか知りたい
●「紙の月」の意味を知りたい
● 自分の未来について考えてみたい
ただ好きで、ただ会いたいだけだった―――わかば銀行の支店から一億円が横領された。容疑者は、梅澤梨花四十一歳。二十五歳で結婚し専業主婦になったが、子どもには恵まれず、銀行でパート勤めを始めた。真面目な働きぶりで契約社員になった梨花。そんなある日、顧客の孫である大学生の光太に出会うのだった・・・・・・。あまりにもスリリングで、狂おしいまでに切実な、傑作長篇小説。各紙誌でも大絶賛された、第二十五回柴田錬三郎賞受賞作
Booksデータベースより-
梅澤梨花・・・主人公。銀行で働く契約社員
平林光太・・・大学生で,梨花と付き合うようになる
梅澤正文・・・梨花の夫。仕事一筋で,梨花とすれ違うようになる
平林孝三・・・光太の祖父。梨花の勧めで定期預金をするようになる
1⃣ 梨花に対する印象
2⃣ 横領に手を染める梨花
3⃣ 梨花の逃亡
プロローグから何かを匂わせる話になります。タイのチェンマイにいる一人の女性。チェンマイからバンコクに入り,自由に生活できるという解放感を味わっているようでした。
この解放感はどこからくるのか。女性は何かを得たのか,それとも失ったのか。自問自答するというところから話は始まるのです。
ここで岡崎木綿子という女性の視点に移ります。彼女は同窓会に参加していました。垣本梨花という同級生が世間を賑わせていました。その女性はある銀行に勤めており「一億円」を横領したとして指名手配されていました。
そこまで仲がよかったわけではないが,関りがあった木綿子は,それがあの梨花なのかという衝撃を受けます。
「自分の知っているあの『梨花』に,一体何があったのか」
木綿子は記憶を辿ります。あの梨花は横領するような女性だっただろうかと。確かに顔立ちなどは綺麗な感じではあったが,自分の知っている梨花はとてもそんなことをするような人間ではなかったはず。
成績は優秀で,誰かに影響を与える人間でもない。リーダーシップを発揮するような感じでもなく,どちらかというと大人しく,一歩ひいて歩くような人間だったと。
それは同級生で,梨花と付き合ったこともある山田和貴も同じでした。まさか自分の知り合いが,いや,付き合ったことがある女性があんな犯罪を犯すなんて,信じられないという様子です。
いろいろな人物の視点で梨花のことが語られるんですけど,梨花が本当に犯罪を犯したのだろうか,と僕自身も疑問に思ってしまうほどです。
そして時は,あの「犯罪」を犯す前の梨花の話に戻ります。
専業主婦をしていて,夫である正文の収入だけで生活していた梅澤梨花。何不自由ない生活をしていたはずでした。学生時代は成績も良く,周りの同級生からも一目置かれる存在だったんですね。
彼女はある日,契約社員として銀行に勤務することになります。主な仕事が,顧客,特に年寄りに定期預金に入ってもらうという営業の仕事をまかされていました。そして、多くの顧客からは細かい気配りができ,評判もなかなかのものでした。
個人的に誘われるような魅力的な部分もあり,ちょっと危なさも感じながらも,上司からはとても信頼されているようです。
そんな顧客の中に,平林孝三という老人がいました。彼はある意味資産家のようで,妻を亡くしてはいるものの,住宅街に100坪くらいの敷地の住宅に1人で住んでいました。
梨花はこの孝三からも定期預金の契約をしていました。ただ,孝三は梨花のことが大変気に入っているようで,あの手この手で誘ってくる人物でした。
でも梨花自身ははあまり深入りしないようにしています。下心のある人物が契約との見返りに迫ってくるというのもうまくかわしていたようです。
そんな中,梨花の心に変化が現れていくのです。
ある日,孝三の家に訪問している時,ある青年と鉢合わせます。彼は平林光太といい,孝三の孫でした。光太は大学生で,資産家の祖父の家に入り,何やら金目のものを探しているような行動を見せていました。
金をせびりにきているふうにも見えるこの光太でしたが,梨花は徐々にこの光太と打ち解けていきます。そして少しずつ距離が近づいてきているようにも見えました。
それと反比例するように,梨花の家庭は徐々に冷えてきているようでした。最初は何不自由のない生活を送っているような梨花も、自分への関心が薄い夫との間には、少しずつ溝ができつつあります。
次第に夫は出張が多くなり,さらには海外転勤の話まで出てきました。やはり,夫との気持ちが離れるにつれて,光太との距離が縮まっていく。まずい予感がします。結局、夫は上海へ転勤が決まりました。そして梨花は光太と急接近し,付き合うことになるのです。
ところが,この光太は映画製作に没頭しており,大学も留年を続けてしまっていました。
しかも多額の借金も抱えていたようです。しかも消費者金融から。早く返さないと多大な利子を付けられて光太が苦しんでしまうかもしれない。
「何とかしないと」と考える梨花。
年上としてのプライドなのか,大好きな男性への献身なのか,彼女はとんでもないことを思いついてしまいます。それは,自分の顧客の定期預金に手をつけるということです。少ない金額であれば,後で返せばよいのだと自分に言い聞かせて。
顧客から定期預金を預かり,それは自分の手元に。そして夫のいなくなった部屋のプリンタを使って,証書を偽造するのです。つまり「横領」です。
最初は「今回だけ」と思っていた梨花の悪事も,どんどんエスカレートしていきます。光太へのプレゼントだけでなく,自分自身の服や美容にカネをつぎ込み,気が付いたら自分の月給以上に毎月の返済額が増えていきました。
こういう悪事に手を染めると,歯止めが効かなくなってくるのでしょうか。梨花は多くの顧客に対して偽の証書を作成し,扱う金額もどんどん増えていくのです。
さらに「スーパーゴールド定期」「プラチナ定期」「ダイヤモンド定期」などなど,ありもしない仮想定期を考え出し,そのための証書も偽造します。
月々に自分の通帳に入ってくる金額が50万,70万と増えていくことに,そこまで罪悪感を感じていないようでした。
そんな梨花に,思ってもないことが起きてしまいます。
※ネタバレを含みますので,見たい方だけクリックしてください!
👈クリックするとネタバレ表示
光太との関係に違和感を感じる梨花。それは光太の行動が最近になって怪しいと思うようになりました。ここで梨花は何と探偵を使って,光太の動向を探ろうとするのです。
ネットで調べても,探偵料というのは事務所によって異なっていて,高いところだと一時間当たり5000円とか6000円とか。
昼夜問わず動き回ることも考えれば,数週間で数百万円とかにまで増える金額です。
そこまでして探偵を雇ったのは,梨花の金銭感覚が麻痺してしまっていたことも大きいのではないでしょうか。
そして梨花は,光太が22歳の女性と仲良くしていることを知らされるのです。
さらには,梨花が証書偽造で横領していたという事実を,他の社員が気づいたのです。
梨花はこれが限界であると悟ったのでしょう。
光太が密かに他の女性と付き合っていたことを言うことなく「私と会ったことや私の存在を忘れて」と言います。
これが梨花と光太の最後でした。そして海外へ逃亡を図るのです。行先は「バンコク」
住んでいた場所も,彼女が使っていた預金通帳も全て手放し,異国の地へ旅立つのです。
そして,バンコクからチェンマイへと移動しようと考えるのです。
「無事に越えられるだろうか。。。」
これが冒頭のプロローグへと繋がっていたんですね。彼女は考えます。なぜこんなことになってしまったのか。夫と出会ったからか。中高一貫の学校へ進学してしまったからなのか。光太と出会ってしまったからなのか。
いろいろと考えを巡らせているところに一人の男性がやってきます。
「パスポートを見せてもらってもいいでしょうか」
この瞬間,梨花は「もう終わりだ」ということを悟るのでした。
この作品のモデルではないかと言われている作品があるようです。
滋賀銀行8億円横領事件
主犯は当時京都市在住だった42歳の女性銀行員。仕事での評価は高く、模範銀行員として行内や顧客から信頼されていた人物でした。
昭和41年(1966年)の11月~昭和48年(1973年)の2月の約6年半にわたって犯行が繰り返され、着服後の金はほぼ全て、共犯である愛人の男に貢がれていました。
愛人の男は交際途中で黙って別の女性と婚姻しており、男に騙され最終的に捨てられた形になった主犯には同情の声も集まりました。主犯は服役中に真面目に刑に向き合い、少しずつ返済も行われました。
夫婦のすれ違い,自分より若い男との関係。タイミング的に偶然なのかなと思いましたが,でもこれって必然だったのではないかなとも思います。
原因は梨花ではなく,夫との関係にあり,次第に気持ちが揺らぎ始めてしまった。
そして心は満たされるも,今度は若い男のために,何も知らない老人たちの定期預金に手をつけてしまった。
全て,因果関係がはっきりしている展開だなと思いました。
人生,何が起こるかわからないなと思いました。自分の置かれた環境によって,人生は良くも悪くもなるのだと。そして最後はその人の人間性によるのだと。彼女は「悪の道」を選んでしまったんですね。
僕自身,ある数学者の講演会に参加したことを思い出しました。
ある子供が万引きをしてしまった。これに対し,あなたはどう思いますか,ということを聴衆に問いかけます。
ある人は「万引きはいけないことだ。犯罪だ」と考える人もいれば,「万引きをしてしまうほど貧しくてかわいそうな人だ」と同情する人もいる。
つまり,人の行動というのはその人の性格,価値観や育った環境で培われた「情緒」に左右されると。
だから,自分の未来がどうなるかなんて本当にわからないなと思います。
本作品を読んで,梨花のことを「犯罪を犯した悪人だ」と思うか「いろんな人に翻弄された可哀そうな人だ」と思うかも,その「情緒」で違うのかなと思いました。
「紙の月」というタイトルの真意はわかりませんが,海外では「ペーパームーン」と言って「儚いもののたとえ」として使われるようです。確かに梨花の人生とは儚いものだったのかもしれないですね。
● 本作品の主人公に対する思いは,人によって異なるということ
● 自分の未来で何が起こるかわからないということ