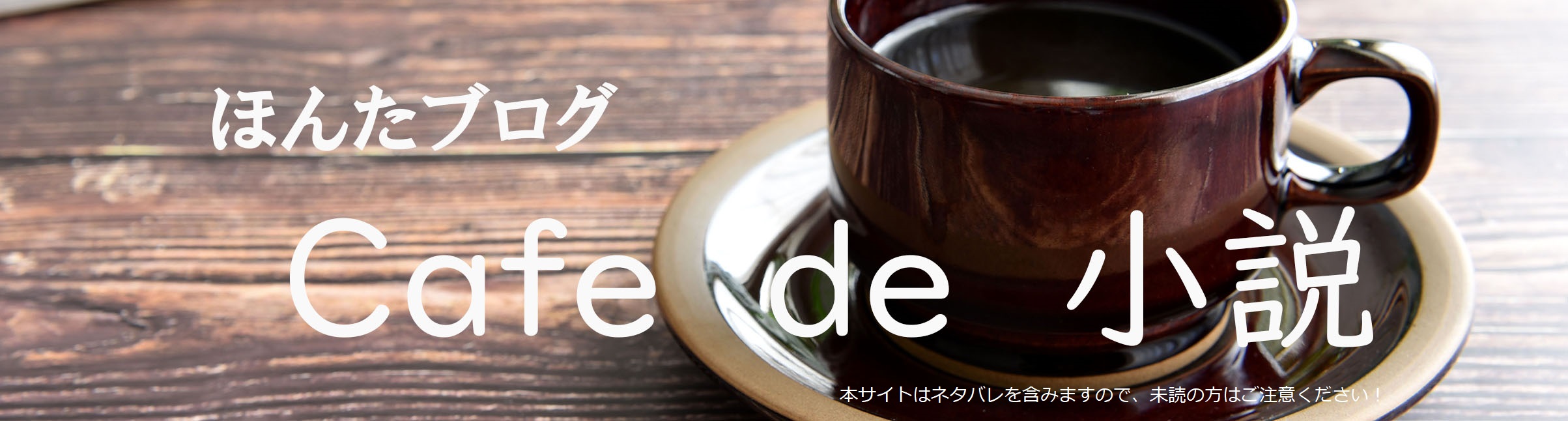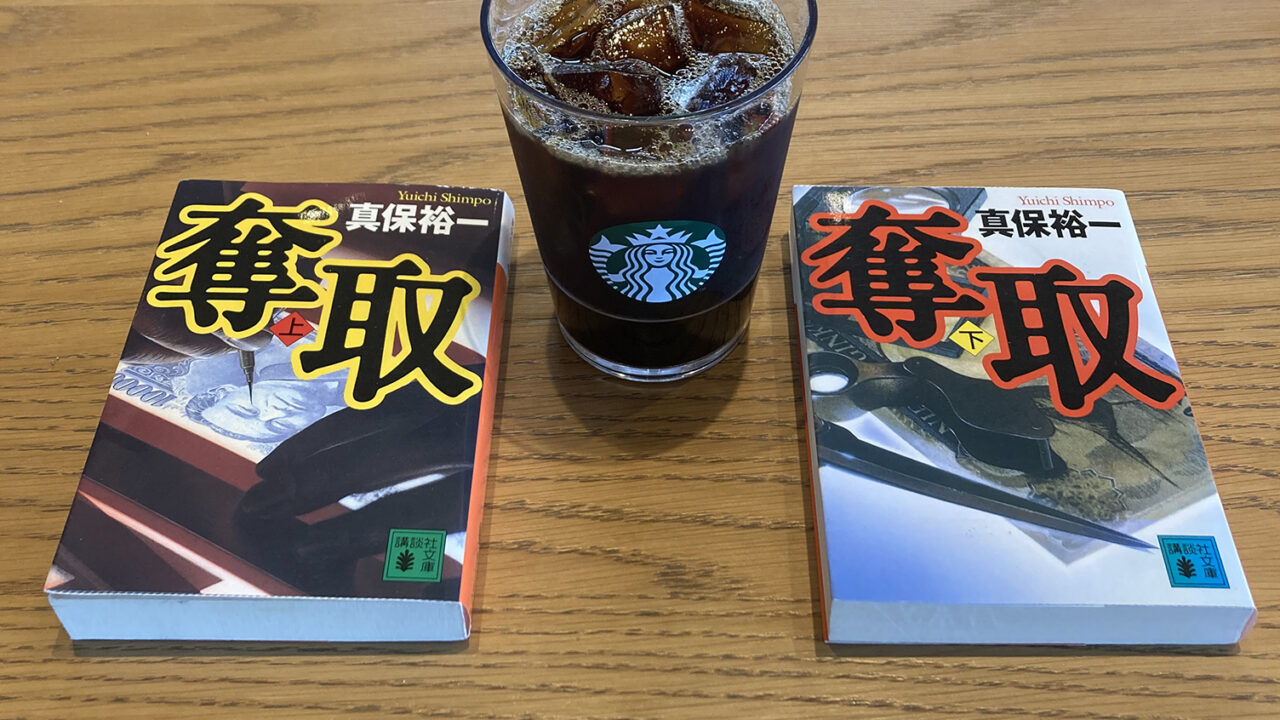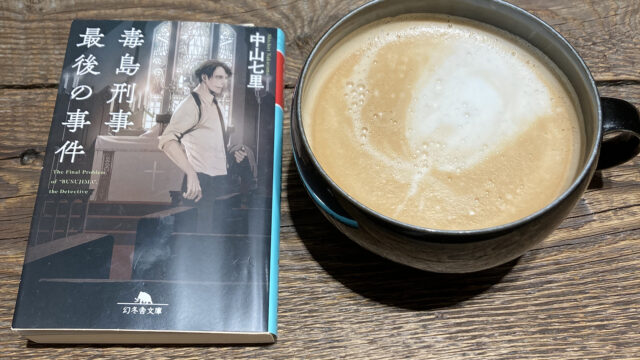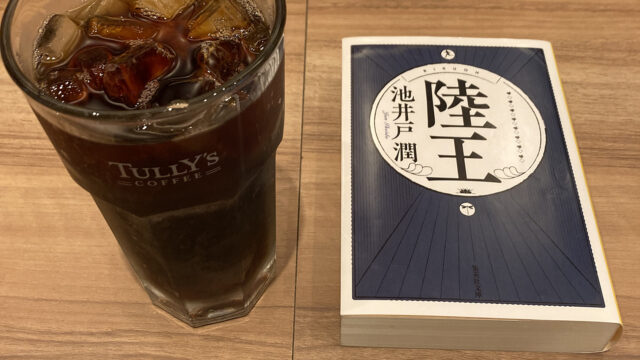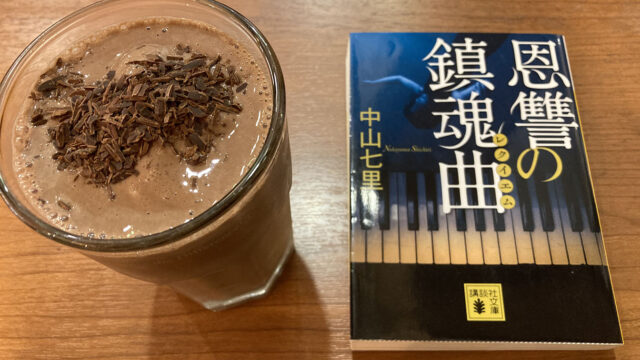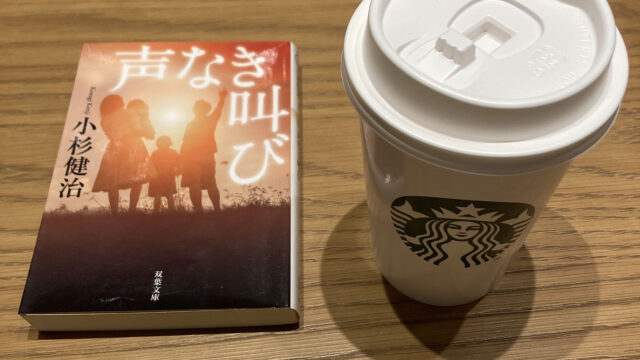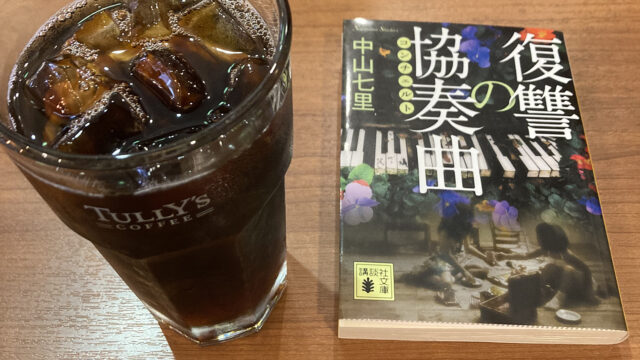真保裕一先生の代表作の一つで,「日本推理作家協会賞」だけでなく「山本周五郎賞」をダブル受賞したすごい作品です。
これまで真保裕一先生の作品は何作か読みました。一番インパクトがあった作品と言えば「ホワイトアウト」かな。それにも勝るとも劣らない作品。
本作品は上下巻になっていて「偽札偽造」の話です。1996年に発刊された,かなり古い作品ではありますが,読み始めてから一気にハマり込みました。
日本銀行が発行するお札の特徴がよくわかりました。透かしだったり,他では真似できない印刷手法だけでなく,多くの手法を組み合わせる技術。よくもここまで調べ上げて描かれたな,と感心させられます。
昨年,新札が登場したばかりだったので,何か「早くこれを読め」と言われているようで新鮮でした。
日本の技術を「偽札偽造」という視点から表現されている貴重な作品だと思います。是非,読んでみてください!
目 次
1. こんな方にオススメ
2. 登場人物
3. 本作品 3つのポイント
3.1 親友を救うため
3.2 新しい仲間との偽札作り
3.3 本作品の考察
4. この作品で学べたこと
● 日本の紙幣の技術の高さを知りたい方
● 印刷技術について詳しく知りたい方
● スピード感あふれるストーリーを堪能したい
偽札をつくりあげた者が勝利者となる!傑作長編
1260万円。友人の雅人がヤクザの街金にはめられて作った借金を返すため、大胆な偽札作りを2人で実行しようとする道郎・22歳。パソコンや機械に詳しい彼ならではのアイデアで、大金入手まであと一歩と迫ったが…。日本推理作家協会賞と山本周五郎賞をW受賞した、涙と笑いの傑作長編サスペンス!
-Booksデータベースより-
手塚道郎・・・主人公。親友の借金を返すべく,偽札偽造を思いつく
西嶋雅人・・・道郎の友人で,1260万円もの借金をして苦しんでいる
水田鉱一・・・偽札偽造のスペシャリスト。道郎に伝授する
竹花幸緒・・・印刷会社の娘。中学生で偽札偽造に協力しようとする
1⃣ 親友を救うために
2⃣ 新たな仲間との偽札作り
3⃣ 本作品の考察
手塚道郎は,自分の親友である西嶋雅人が1260万円もの借金を抱えていることを知ります。もちろん雅人は返せないため,暴力団に監禁されていました。何とか救い出したい道郎でしたが,何と道郎はいつの間にか雅人の保証人になっていました。
東建ファイナンスという名前ですが,実質暴力団。そこには佐竹という男と,さらにその上司っぽい江波という男がいます。とうとう道郎も彼らに捕まってしまいます。そしてとんでもないことを言われるのです。「一週間以内にカネを返せ」と。
こんな大金をたった一週間でどうやって返すのか。いろいろな手段を考える道郎はとんでもないことを思いつきます。それが「偽札偽造」です。
バレたら日本に対しての反逆,まさに国家を揺るがす大事件になります。これをやってしまおうとする道郎の心理はちょっと理解できない。過去にもそんな大事件が起こっていたようです。
チ-37号事件とは
1960年代に発生し戦後最大の偽札事件として知られる「チ―37号事件」は聖徳太子が描かれた千円札が偽造され、全国で300枚超見つかった。
肖像が初代首相の伊藤博文へ変更されるきっかけになった。 直近10年で平均すると年約1800枚の偽造紙幣が見つかっている。
-日本経済新聞サイトより-
紙幣の価値は昔の方が高いはずなので,とんでもない大事件だったということは想像つきますよね。この偽札を創ろうというのが道郎の計画です。ただ,完璧な印刷を目指したわけでなく,偽札判定器の盲点を突く札を作ろうとしたのです。
道郎たちが狙うのはキャッシュディスペンサー(現金自動支払機)ではなく,ATMです。つまり,入金機能があるATMに偽札を投入し,その残高を別の場所で引き落とすという手法。なるほど,入金時の札のチェックに引っ掛からなければ,道郎たちは大金を入手したことになるわけです。
ところがこのチェックが何重もの厳重なチェックが行われる。どんなチェックが行われるかを道郎は図書館で多くの参考文献を元に推理します。きっと同じように,作者も多くの参考文献を読み漁って本作品を仕上げたのではないかというのは容易に想像できます。
道郎がやらなければならないことは他にもありました。それは事前に偽札チェッカーの機械を入手することでした。そのためには,本物のATMに組み込まれている機器を盗まなければならない。そこで道郎は電線に発火装置を取り付け,時限的に発火させ火事を起こして警察の気をそちらに引き付けている間に,別の場所のATMで偽札チェッカー器を盗もうという計画なのです。
本作品が描かれているのが2000年代前半なので,現在同じような手口でこのATMに攻撃を仕掛けることが成功するかはわかりませんが。とにかく,この計画は成功し,道郎たちは偽札チェッカー器を強奪することに成功するわけです。
そこから道郎はいろんな種類の紙,インク,プリンターなどを仕入れ,この「チェック」から逃れるための偽札を作ろうと試みます。一週間という短い期限の中で,必死に試行錯誤をした結果,とうとうこの「チェッカー」に引っ掛からない偽札を作り出すことに成功するのです。そしていくつかの銀行にあるATMに並び,換金することにします。
これが成功するのかどうかというのが一つのポイントです。
道郎たちの実行は成功していきました。ところがこの行動を怪しんでいる様子の老人がいるのです。彼の名は水田紘一。道郎たちが転々とする銀行店舗の先々に現れる水田。この老人は一体何者なのか。敵なのか,味方なのか。
順調にいっていた感じの道郎でしたが,ここで東建ファイナンスの連中に感づかれます。どうやってカネの作ったのか,道郎たちの計画はバレバレでした。ずっと道郎たちの行動を尾行していた者がいたんですね。
そして道郎は東建ファイナンスに捕まってしまいます。これで万事休すかと思われましたが,ここであの水田が現れるのです。実は彼は道郎の行動を監視していましたが,むしろ味方でした。軽トラックで道郎を辛うじて救い出しました。
ただ道郎の相方の雅人は助け出せませんでした。結果的には道郎は雅人を警察に売るのです。ここは難しいところですが,雅人が東建ファイナンスの手に渡ってしまうよりは,警察に通報して刑務所にいる方が安全だという,苦渋の判断だと思います。
警察からの取り調べに雅人は何を話すのか。道郎は後ろめたさを感じながらも,水田と一緒に行動するようになります。水田という人物は一体何者なのかというところですが,彼は印刷業界に携わっていた経歴があるようです。
ここで道郎は水田の知り合いに頼み,別の人物へ戸籍を変更し,保坂仁史に成り代わわることになります。水田の知り合いの娘である幸緒(さちお)は,印刷会社の娘でした。保坂,水田,幸緒の三人で計画したのが「真の偽札を作ること」でした。
かつて道郎がチェッカーをかいくぐるお札を作るというレベルでなく,見た目や質感などを完璧にしたお札。その技術に保坂は驚くわけです。そして印刷会社に入社することになります。印刷の技術や知識を,印刷機の特徴を知るために。
ただ問題もありました。幸緒の家の印刷会社は,銀行から融資を止められそうになっていました。そこに大型チェーンのコンビニを建てる計画。そしてとの銀行と裏で繋がっていたのがあの東建ファイナンスだったのです。ここまで繋がりがあるとは。。。
三人の知識を合わせ,本物に限りなく近い札を作り,その資金を元手に印刷会社を立て直そうとするわけです。お札にはいろいろな技術があることが本作品でも描かれています。私たちでもよく知っているのは「透かし」の技術でしょうか。
本作品でよく登場するのは「ミツマタ」という植物が使用されているということです。
ミツマタ(三椏)とは
ジンチョウゲ科ミツマタ属の落葉低木。
中国中南部・ヒマラヤ地方が原産地とされ、冬になれば葉を落とし、春には白や黄色の花を付けます。
枝が3つに分かれることから名付けられ、樹皮の繊維は和紙や紙幣の原料としても用いられます。
日本の紙幣は偽造防止の最高峰レベルらしいです。それでも三人はこの難易度の高いプロジェクトに挑戦するのです。そして彼らはとうとう偽札を完成させます。東建ファイナンスとの取引は成功するのか。
この先は実際に読んでほしいと思います。上下巻を読み切るのに,意外と時間がかからないほどのスピード感でした。
本作品を読んで思ったのは,まずは日本のお札が最高レベルの技術を結集させた至極のものであるということです。2024年に新札が発行され,さらにその技術は他の追随を許さないものになっていると思います。ネットでどんな技術が使用されているかということが堂々と載っています。
日本のお札
世界でも屈指の偽造抵抗力を持つと言われる日本のお札について紹介します。時代の移り変わりとともに進化し、流通環境への適性が求められるお札には、高度な偽造防止技術がいくつも施されています。
お札のことをよく知り、偽札に騙されない確かな目を持つことが、偽札に対抗する最も有効な防御手段となり、日本の通貨そのものに対する信用や信頼につながります。
-日本造幣局サイトより-
ここまで細かく説明しているサイトがあっても,日本の技術が他に知れ渡ってしまおうとも,実現するのはとても難しいのだろうと思います。敢えてここまで載せるのは,ある意味「偽造」の難しさを知らしめ,抑止力になっているという考えもできます。これらの技術を手に入れるにはきっと多大な労力や資金がかかるでしょうから。
それらの技術をベースに,本作品のストーリーを作り上げた作者の作品へかける想いは相当なものだったと思います。もちろん偽札を作ることは大罪であり,それを実行しようとするのは国家に対する冒涜であるとも思います。
きっと「この類の作品を描いてもいいのだろうか」と何度も自問自答したのかもしれません。それでも敢えて描いたのには相当な勇気と覚悟があったのではないか。それも含めて総合的に評価されたからこそ,2つの賞を受賞できたのではないでしょうか。
先にも書きましたが,スピード感満点のストーリーと難易度の高い知識が結集した見事な作品だと思うので,是非ご一読を!
● 改めて,日本の紙幣の作製技術の高さを知ることができた
● 日本紙幣の特徴を追求し,それをベースにストーリを作った作者に感服でした