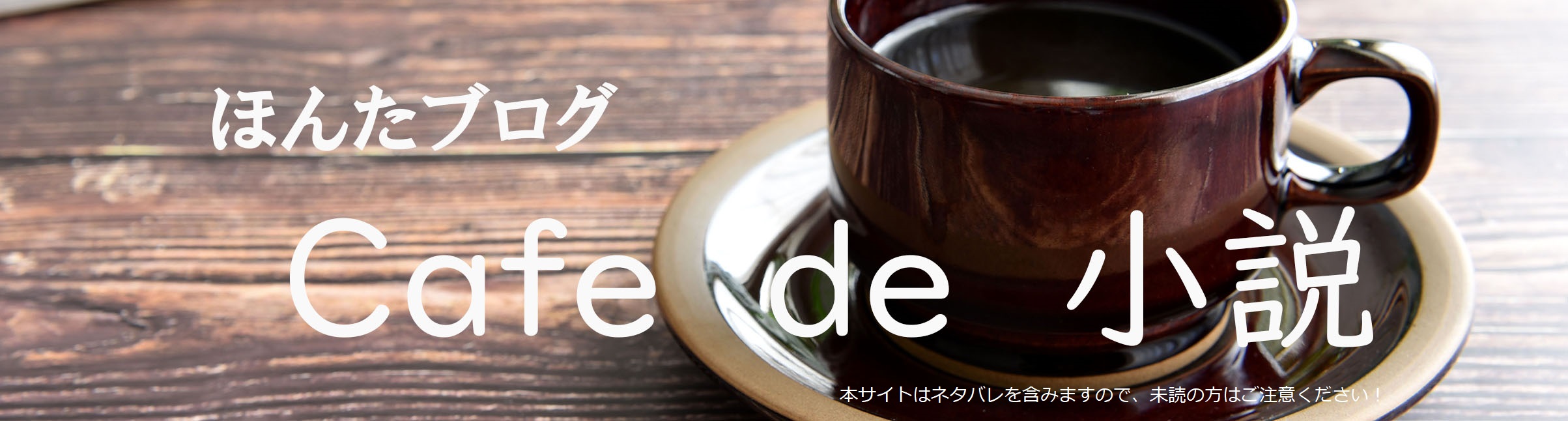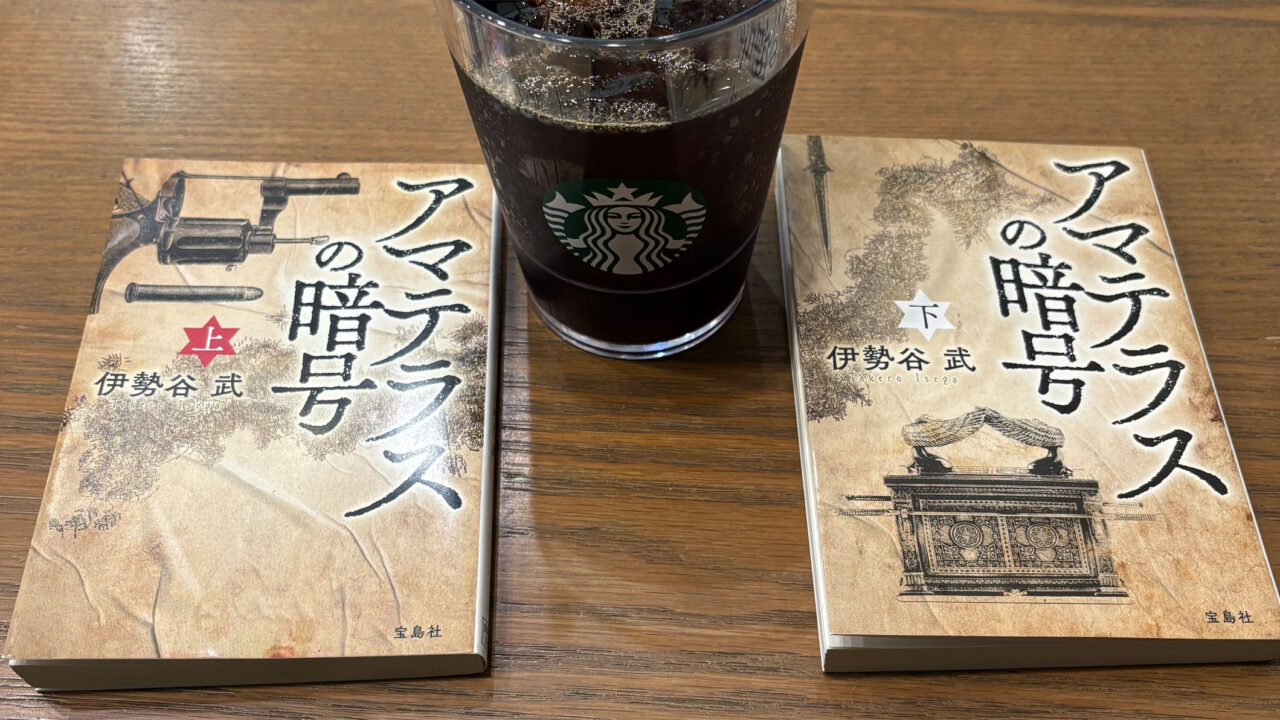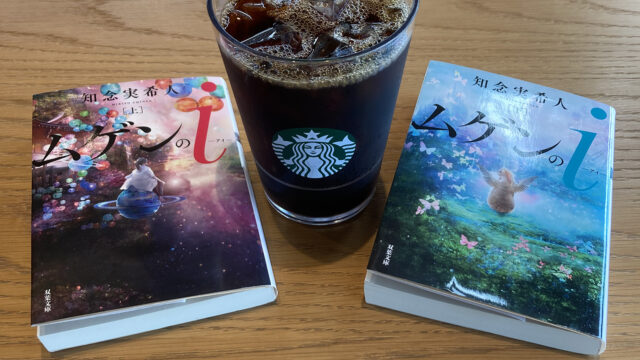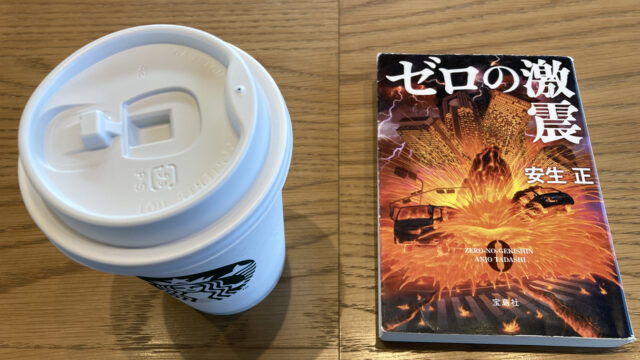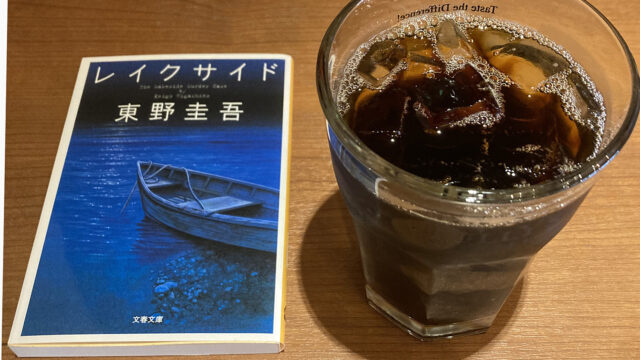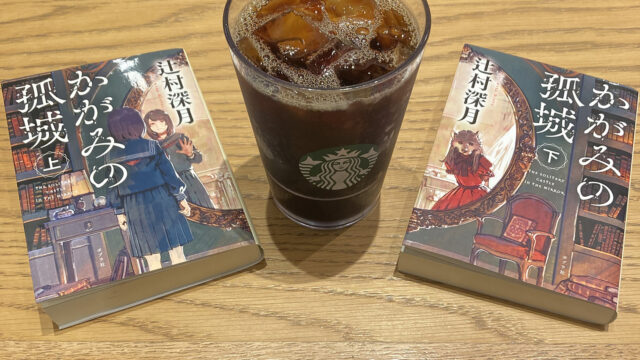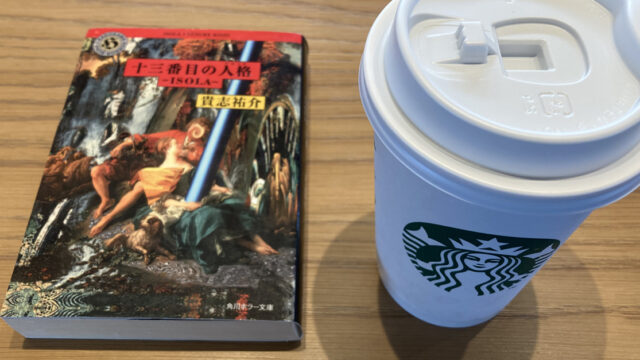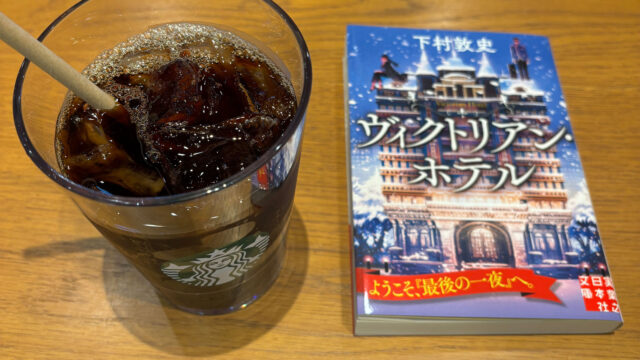あの「ダ・ヴィンチ・コード」を超える謎に迫る!
これが書かれた帯を見て、すぐに購入した本作品。上下巻で構成されています。
世の中には多くの宗教があります。キリスト教、イスラム教、ヒンズー教など、昔、歴史の授業で習ったのを思い出します。そして日本にも伝え渡ったという背景もあります。
日本で特に信仰が多いのは仏教であり、ただそこには多くの宗派もあります。浄土宗、浄土真宗、曹洞宗、真言宗、日蓮宗などなど、他にもたくさんあるというのは歴史の授業でも学びましたよね。あまり覚えていませんが・・・
そして本作品の焦点になっているのが「神道」です。古くは天照大御神(あまてらすおおみかみ)がいたとされ、それは日本の皇室にも受け継がれているものです。
本作品は、神社の宮司で主人公の父親が何者かに殺害され、その真相を突き詰めるという作品です。主人公は仲間と行動しながら、この「神道」の謎にも迫るという、なかなか読んだことがない小説でした。
神道自体の知識も浅い僕はこの作品を通していろいろなことを知ることができました。きっと作者の伊勢谷武先生も「神道の神髄」について伝えたかったのではないかと思います。
特に「神道」を信仰している方には意外な事実もわかって面白いと思います。
信仰していない方にも、日本という国がそれを礎に発展してきたという歴史的背景を知ることができますし、とても興味深く読めると思います。
是非、読んでみてください!
目 次
1. こんな方にオススメ
2. 登場人物
3. 本作品 3つのポイント
3.1 父親が殺害された理由を探す主人公
3.2 日本の起源と世界との繋がり
3.3 本作品の考察
4. この作品で学べたこと
● 日本の神道に興味がある方
● アマテラスの暗号とは何なのかを知りたい
● 日本が古くから受け継いできたものを知りたい
ニューヨーク在住の賢司は、日本人父との四十数年ぶりの再会の日、父が殺害されたとの連絡を受ける。父は日本で最も長い歴史を誇る神社のひとつ、丹後・籠神社の宗家出身、第八十二代目宮司であった。
籠神社は伊勢神宮の内宮と外宮の両主祭神(アマテラスと豊受)がもともと鎮座していた日本唯一の神社で、境内からは1975年、日本最長の家系図『海部氏系図』が発見され、驚きとともに国宝に指定されていたことで知られていた。
神職に就く父が何故日本から遠く離れた国で殺されたのか? 再会の日、父が自分に伝えたかった事とは?
父の死の謎を探るため、賢司は友人たちと日本へ乗り込むが……
写真、図など豊富な資料を用いて、日本の歴史に挑む新感覚の歴史ミステリー!
Booksデータベースより-
1⃣父親が殺害された理由を探す主人公
2⃣ 日本の起源と世界との繋がり
3⃣ 本作品の考察
ニューヨーク、ゴールドマン・サックス社に勤めていた賢司・リチャーディー。その会社を辞めた賢司の元に、ある人物から連絡が入ります。それは、遠く離れた日本で暮らす父親でした。
賢司の両親は離婚していて、父親とはしばらく連絡をとってませんでした。それだけに急に連絡を寄こしてきたことに対して少しばかり戸惑いを感じている様子。
しかし、ニューヨークで親子が会うことになっていたその日、ある事件が起きます。賢司の元に今度は警察から連絡が入ります。何とそれは「賢司の父親が何者かに殺害された」という知らせでした。
賢司は思うのです。「父親は何を自分に伝えようとしていたのか」と。その真実を知るべく、賢司は日本へ行くことにするのでした。
賢司の父親は籠(この)神社の宮司でした。
籠神社について
神代と呼ばれる遠くはるかな昔から奥宮の地眞名井原に匏宮(よさのみや)と申して豊受大神をお祀りして来ました。その御縁故によって第十代崇神天皇の御代に天照大神が倭国笠縫邑からお遷りになり、天照大神と豊受大神を吉佐宮(よさのみや)という宮号で四年間ご一緒にお祀り申し上げました。
その後天照大神は第十一代垂仁天皇の御代に、又豊受大神は第二十一代雄略天皇の御代にそれぞれ伊勢にお遷りになりました。その故事により当社は伊勢神宮内宮の元宮、更に外宮の元宮という意味で「元伊勢」と呼ばれております。
-山陰道一之大社 籠神社サイトより-
本作品でも書かれてしますが、現在「天照大神」を祀っているのは伊勢神宮なのですが、賢司やナオミたちの調査の結果、伊勢神宮に遷ってくる前はこの籠神社に祀られていたようなんですね。
そして豊受(とようけ)大神とは、この天照大神に食事を与えていたという言い伝えがあり、現在は豊受を祀っているというわけです。
賢司たちは、神道の最高神と言われる天照大神をかつて籠神社が祀っていたという事実が今回の事件に大きく影響しているのではないかと疑うのです。
「アマテラスの暗号」が書かれた文字は一見、日本人にも読めそうな文字でした。カタカナでかかれたのではないかという文字なんです。
籠神社の起源は真名井神社だそうです。この神社は奥宮であり、かつては別の神紋を付けていました。それが何と六芒星(ろくぼうせい)ダビデの星。つまり、イスラエルの国旗に描かれているものと同じだったのです。
神道はユダヤ人と関係があったのではないか。賢司たちは想像するわけです。本作品では、このユダヤとの関係が時折登場します。読んでいるうちは、それが真実かどうかはわからないんですが、あまりにも共通点が多すぎることに興味が湧いてきます。
遠く離れた島国日本と中東の国イスラエル。イスラエルが信仰する「ユダヤ教」には何か繋がりがあったのではないか。
例えば、ユダヤ教のアーク(聖櫃)と日本でお馴染みの神輿の形がとてもよく似ていたり、ユダヤ人が東を目指して移動しようとした時期と、天照の時代がリンクしていたり。他にもたくさんありますが、果たしてこれは偶然なのかどうなのか、
本作品では多くの写真や図、そしてアマテラス時代からの系図など、よくここまで調べ上げたなと思うくらいたくさん登場します。
それらを見聞きしながら、賢司たちは懐疑的ながらも、心の奥底について離れない部分でもあるように思えてくるのです。
日本には天皇がいますが、現在は126代となっています。初代は「神武天皇」です。
ネットで天皇の家系図を見てみると、私たちが歴史の教科書で学んだ天皇もいます。奈良時代の聖武天皇(第46代)、平安時代の桓武天皇(第50代)、もっと辿れば聖徳太子の飛鳥時代の推古天皇(第33代)、さらには大阪府堺市にある前方後円墳、仁徳天皇陵、これでも第24代天皇なので、初代の神武天皇がいかに遠い昔の時代の人物だったのかがわかるわけです。
逆に天照大神から辿っていくとその上にはこの国を作ったとされる人物がいます。
それは、「君が代」の「き」「み」の起源とされる「イザナ(ギ)ノミコト」「イザナ(ミ)ノミコト」のことです。これはあくまで一つの説であるので真意はわかりません。
天照大神の孫が「瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)」、その下は「うみさちやまさち」の神話で有名な「海幸彦」「山幸彦」がおり、山幸彦である彦火火出見尊(ヒコホホデミノミコト)の孫が神武天皇ということになっています。
また、天照には弟がいます。それが「スサノオノミコト」です。スサノオは聞いたことがあるのではないでしょうか。神話上は、気性が荒い存在であり「暴風の神」と言われ、かつては出雲地方で、あの「ヤマタノオロチ」を退治したと言われる神です。島根県の須佐神社に祀られているようです。
これはあくまでも「神話」に登場する人物たちではありますが、日本という国が、いかにこの伝説(本当かもしれないですが)を代々受け継いできているかがわかりますよね。
このように、日本にいろいろな神話が残っているのは、神道を未来へ残そうとしていることの表れではないかとも思うのです。
ちょっと話はそれますが『君が代』と言えば、卒業式や入学式で必ずといっていいほど歌われますが、これは都道府県によっても異なるようです。
戦前「君が代」は天皇崇拝の象徴として日本の軍事侵略の道具として使われた歴史があったため『君が代』を歌うことに抵抗感を抱く人がいるということです。
これを聞くと、2011年に当時大阪府知事だった橋下徹さんのことを思い出します。
国歌斉唱の際に起立をしなかったことで処分を受けた大阪府立高の元教諭の男性が、定年後に再任用を拒まれたのは違法だとして裁判を起こしたことがありました。
その後、公立校の教職員に君が代の起立斉唱を義務づける全国初の条例案が可決されました。憲法19条に保障された「思想・良心の自由」において、個人が強制的に「君が代」を歌うことを拒否する権利を保障しているという見解もあるため、いろいろな観点から問題になりました。
確かに歴史的背景や人の価値観で捉え方はは人それぞれなのだなと思いますが、この『君が代』自体を純粋に捉えてもよいのではないかとも思います。
「君が代」は、平安時代の古今和歌集に収められた「わが君は千代に八千代に さざれ石の巌となりて 苔のむすまで」が元になっているようです。
『国の繁栄や平和、安定が永遠に続くように』という願いを込めた歌詞となっているわけなんですね。
実際、宮崎県にある「狭野神社」は神武天皇誕生の地とされていますが、『世界がこれからも平和でありますように』という言葉が掲げられています。
オリンピックで日本国歌斉唱の際、海外の人々がその歌詞の意味を知り、感動したというのを聞きました。
ほとんどの国の国歌は、祖国を愛する歌であったり、国王への祈り、過去の英雄を称るような歴史上の出来事を歌ったものなどが多い中、『世界平和を願う』という、次元の異なる歌を国歌としているところはとても稀であるようです。
話は逸れましたが、賢司たちは調査しながら、また異国との共通点を見つけてしまいます。
神社の入り口には必ずと言っていいほど「鳥居」がありますよね。現在のシリアで話されているアラム語というのがあるんですが、アラム語で入り口のことを「トリイ」というそうです。そして意外だったのが、イエスキリストが通常話していたのがこのアラム語らしいのです。ただ、イエスは「ヘブライ語」も話せたといいます。ヘブライ語はイスラエルの公用語です。
これは何かの偶然なのかどうなのか、いろいろ知っていくと世界って一つに繋がってしまうのではないかと思ってしまいます。
日本の遠い過去の歴史、そして世界との繋がりをも感じさせる作品です。
僕自身が育った家にも神棚があり、親が毎日柏手を叩き、拝んでいるのを見よう見まねで覚えていきました。
ただ、強い信仰心があったわけでもなく、神棚に手を合わせるだけ。ある日、母方の実家へ行った時には仏壇があり、いつものように柏手を叩くと「ここでは手を叩かないんだよ」と言われたのを思い出しました。そこで初めて世の中には多くの宗教があり、その慣習にもいろいろ違いがあるのだと思ったのを覚えています。
日本って、いろいろな宗教を信仰する人々がいますが、そこまで厳密に信仰していないような気がします。初詣で神社に行く人、お寺に行く人が大勢いますが、かと言って自分の宗教に従っているようでもない。例えば結婚式でも、式自体を神前式で挙げる人もいれば、教会(チャペル)で挙げる人もいますもんね。
それだけでも日本というのは特別な国なのかもしれません。
本作品の最後はやはり日本の「神道」とは一体何なのか、賢司の父親が触れてしまった「タブー」とは何だったのかということにつながって行きます。最後まで読むと意外な真実が待っていて、正直驚きました。ここでは敢えて書きませんが。。。
そして最後の伊勢谷先生の「あとがき」も読んでみてください。これも敢えて書きませんが、ただ思ったのは、私たちが今、目にしているものや伝え聞いたことというものには、誰かの意図で捻じ曲げられたものがあるのではないか、ということです。
確かに真実を知りたいと思い、徹底的に調べることも重要かもしれません。ただ、あまり踏み込まなくてもよいものもあるのではないか、そんなことも考えたりしました。
伊勢谷先生は自分の足で多くの神社を巡ったり、多くの資料を調べたりされたのだと思います。この作品に多くの写真や図が使用されていることからもそれはわかります。
この作品を創ってくれた伊勢谷先生に感謝したいと思います。
● 日本の神道について詳しく知ることができた
● 日本の起源が意外なものだったことに、ただただ驚嘆した