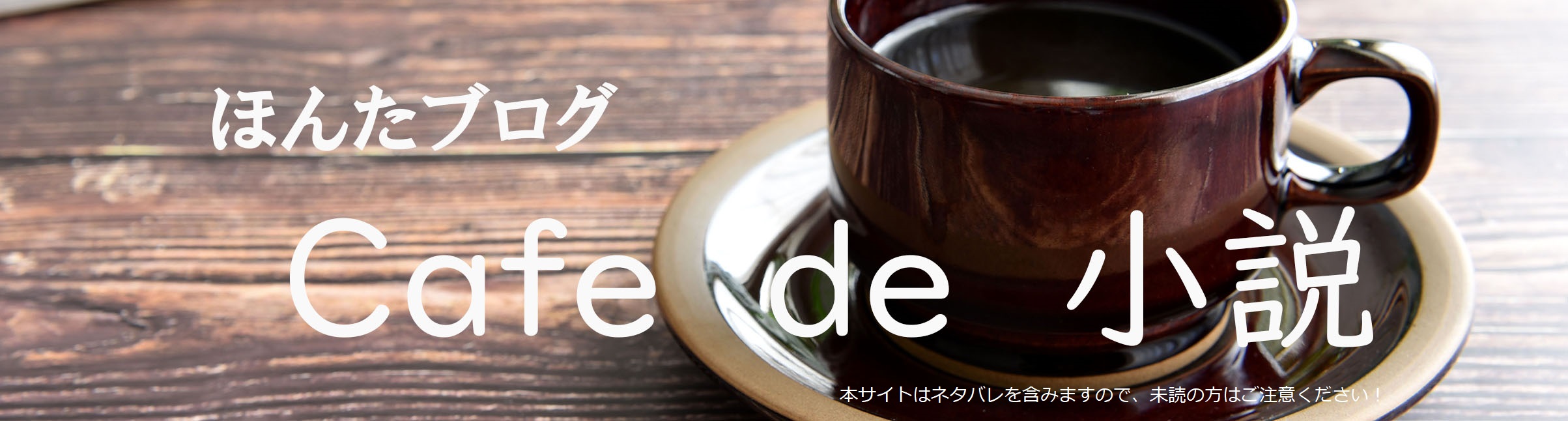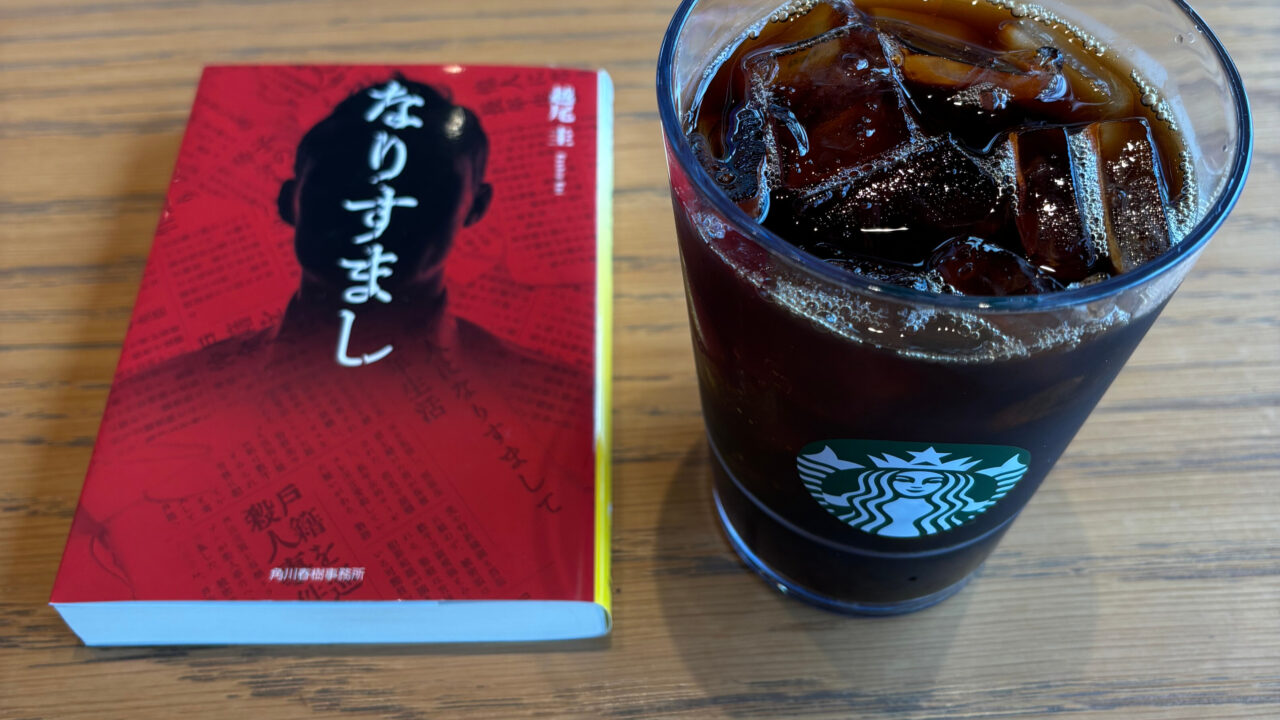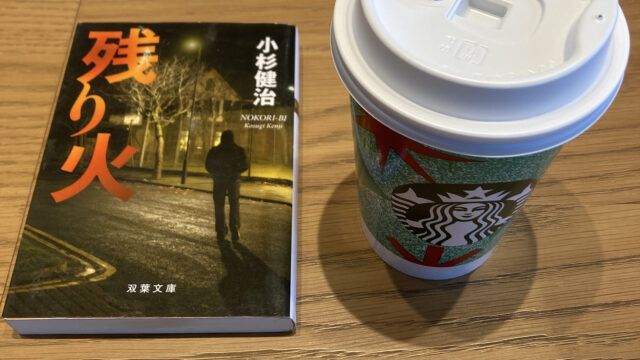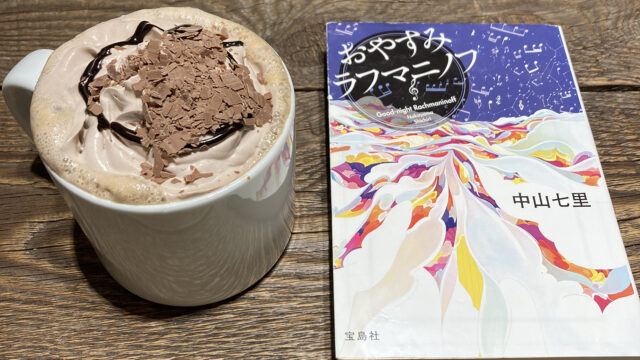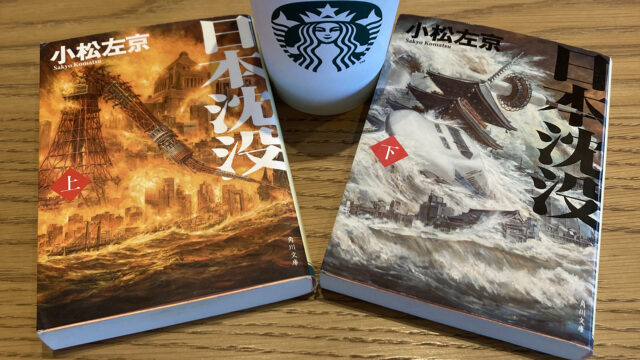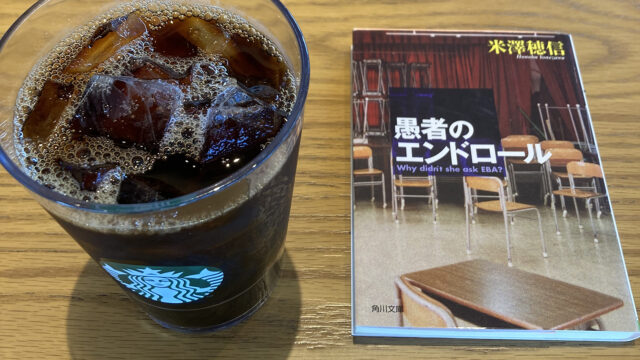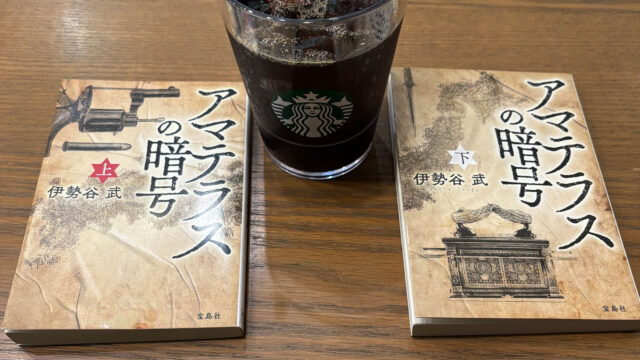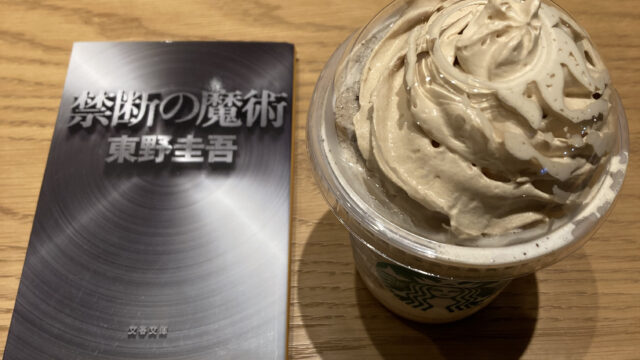名前を変えれば、人生はやり直せるのか。過去を捨てて、別人として生きることは本当に「自由」なのか。
本作品の表紙を見た時、最初は「ネット上のなりすましの話なのかな?」って思いながら裏表紙を見て「戸籍の乗っ取り」の話だとわかりました。
それを見た瞬間に宮部みゆき先生の「火車」を思い出しました。戸籍を変えて、逃亡を図るのにはある理由があったという話。
今回の越尾圭先生のお名前は初めて知りました。新人の作家さんなのかなと思ってましたが、僕と年齢もかなり近い。ちょっと親近感が湧きました。
読みながら、身分を偽って生きる夫婦の物語を通して「自分とは何か」という根源的な問いを私たちに突きつけてきました。
愛する家族と過ごした時間が、すべて偽りの上に築かれていたとしたら、それでもその人生は「本物」と言えるのでしょうか。
僕の周りの人々はみんな「正しい」人たちなのだろうか、と考えさせられました。
とても読みやすい作品なので、是非読んでほしいと思います!
目 次
1. こんな方にオススメ
2. 登場人物
3. 本作品 3つのポイント
3.1 主人公に起こる重大事件
3.2 戸籍に関する日本社会の闇
3.3 本作品の考察
4. この作品で学べたこと
● 戸籍の受け渡しがどのようにして行われるのか知りたい方
●「なりすまし」を実行した意外な人物のことを知りたい
● 自分に戸籍があることのありがたさを感じたい方
ある朝、夫婦でブックカフェを経営している和泉浩次郎が娘の杏奈を連れて出勤すると、妻エリカが店内で惨殺されていた。その捜査の過程で、エリカが戸籍を偽っていたことを告げられる。
妻はいったい何者で、誰が殺したのか?
激しく動揺する和泉だったが、実は彼も戸籍を偽る「なりすまし」だった。焦燥する和泉を嘲笑うかのように、娘の杏奈も殺されてしまう。いったい彼の周囲で何が起きているのか……?
戸籍売買、無戸籍児、そして「なりすまし」──暗部を描き切った社会派小説の傑作!
Booksデータベースより-
和泉浩次郎・・主人公。カフェを経営。本名は七瀬堅吾
和泉エリカ・・浩次郎の妻。実は彼女も戸籍を変更していた
加々美咲月・・・エリカと戸籍を交換した人物
福浦・・・浩次郎とともに事件の真相に迫る
1⃣ 主人公に起こる重大事件
2⃣ 戸籍に関する日本社会の闇
3⃣ 本作品の考察
和泉浩次郎は、東京の片隅で静かな生活を送っていました。彼はカフェを経営し、客足は少ないながらも本に囲まれた穏やかな日常を大切にしています。家庭も円満で、聡明な妻・エリカと、幼い娘・杏奈とともに、平和な毎日を築いていました。
しかし、ある朝、娘・杏奈を連れて出勤した浩次郎が目にしたのは、ブックカフェの床に倒れて血を流す妻の姿でした。妻の名前を叫ぶも、返事はありませんん。明らかに何者かに襲われ、命を奪われたエリカ。突然の悲劇に呆然とする浩次郎。
しかし、事件はこれで終わりませんでした。警察の捜査によって、エリカが「他人の戸籍を使って生きていた」ことが明らかになったのです。つまり、浩次郎の妻は「本当のエリカ」ではなく、まったく別の人物が「加々美咲月」という名前を名乗って生活していたのでした。
つまりこの部分が本作品のタイトルの「なりすまし」ということなのです。
その事実に浩次郎は驚きます。しかしさらに驚くべきことがありました。なんと浩次郎自身もまた「和泉浩次郎」という名前ではなかったのです。
彼の本名は「七瀬堅吾」と言いました。彼もまた、他人の戸籍を使って生きていた「なりすまし」だったのです。
浩次郎が戸籍を偽っていた理由。それは誰にも語れない彼の過去の出来事にありました。10代のころ、実兄が暴力団と関わりを持ち、兄が暴力団の一人を殺害してしまったのです。この重大な事件に関与したことで、堅吾一家は暴力団から報復の標的にされる可能性が生まれてしまったというわけです。
身の危険を感じた堅吾は、すべてを捨てて逃げることを決意します。「ストレンジャー」という名前で活動していた男から、ホームレスの戸籍を買うのです。その名前こそが「和泉浩次郎」です。彼は和泉浩次郎として新たな人生を歩み始めたのでした。
つまり、この夫婦は、互いに「なりすまし」であることを知らずに出会い、結婚し、家庭を築いていたという奇妙な運命にあったのです。二人とも本名を隠して生きていた。
しかし、偽りの身分であっても、ふたりの間にあった愛は本物でした。浩次郎はエリカを心から愛し、娘・杏奈との時間をかけがえのないものとして慈しんでいた。
一体、誰がエリカを殺害したのか。彼の中には、兄のことが頭に浮かびます。ひょっとして、兄が出所して、幸せに暮らしている和泉を探し出し、復讐しようとしたのではないか。
いろいろなことが頭の中を駆けめぐる浩次郎でした。
和泉が悲しみに暮れている中、さらなる悲劇が起こってしまいます。今度は娘・杏奈が突然失踪してしまうのです。保育園の職員が彼女と一緒にいたことがわかります。そして、その職員が目を離した隙に、杏奈は消えてしまったのです。
和泉は懸命に杏奈を探そうとします。ところが思ってもないことが和泉を襲います。数日後、何と杏奈が遺体で発見されてしまったのです。
わずか数日のうちに、愛する妻と娘を失った浩次郎。社会からも不審の目で見られ、警察からも事情聴取が続く中で、彼は精神的に追い詰められていきます。
そんな折、彼のもとをある女性が訪れます。加々美咲月と名乗る女性でした。実は彼女は、「エリカ」は自分の名前を騙って生活していた「なりすまし」だと語り出すのです。
もし自分がいなくなったら浩次郎へ事実を伝えてほしい、そう告げられていた咲月は、ここから和泉と行動することになります。
さらに心強い味方である知り合いの福浦とともに、和泉の正体、そして妻だったエリカの生い立ちを調査していくのです。ただ、和泉親子を追っていた警察は、和泉に不用意な行動を慎むように伝えます。
警察は何か不信感を持っていました。エリカの戸籍が「なりすまし」だったこともそうですが、和泉自身も何かを隠しているのではないか。和泉は警察からの問いをかろうじてかわすのです。
だが、事態はさらに複雑な様相を呈していきます。この加々美咲月と名乗る女性の言葉から、浩次郎の妻が「加々美咲月」としての戸籍を持っていたことは事実だが、彼女自身もまた、その戸籍を別の人物から譲り受けた「なりすまし」だった可能性が浮かび上がったのです。
つまり、浩次郎の妻は「なりすましのなりすまし」だったという複雑な構造になっているわけです。その人物の本名や正体は、結局のところ誰にもわからない。和泉は途方に暮れている様子です。
この連鎖する「なりすまし」の背景には、日本社会の影がありました。戸籍制度に取り残された人々、例えば、親に放置された子供、虐待から逃れてきた少女、DVの加害者から逃れたい女性、前科を持つ者、あるいは誰にも知られず人生をやり直したいと願う人々など。
そうした人々が、戸籍を持たないまま、あるいは過去を捨てるために他人の名前を必要としているという実態があるのです。和泉の妻も何かしらの理由で戸籍を持たない女性だったのです。
浩次郎の妻は、過去に深い傷を負い、誰でもない自分を消すことで人生をやり直そうとしていたんです。そして浩次郎自身も、兄の起こした事件によって自らの存在そのものが危険にさらされ、命を守るために名前を捨てていた。ここに社会の闇が潜んでいることを実感するのです。
ふたりの出会いは偶然でした。しかし、偽りの名前でしか生きられなかったふたりが、お互いの素性を知らずに家族を築いたことに、ある種の運命のようなものが感じられます。名前は偽りでも、家族として過ごした時間には嘘はなかったはずだと、和泉も考えるのです。
警察の捜査が進むにつれ、杏奈とエリカの死の背景には、浩次郎の過去に関わる者たちの存在が浮かび上がってきます。兄の事件で傷ついた人物や、その家族、そして暴力団関係者など、過去に置き去りにしたはずのものが、数十年の時を超えて浩次郎のもとに返ってきたのだった。
浩次郎はすべての真実を受け入れ、誰にも語れなかった過去と向き合っていくことを決意します。娘を殺した犯人は誰だったのか。なぜエリカは殺されなければならなかったのか。そして、彼自身は本当に「自分」として生きていたのか。
真相は、誰か一人の悪意によるものではなく、さまざまな人間の過去と痛みが交錯した結果でした。浩次郎の人生は、偽りに満ちていたかもしれない。
しかし、その中に確かに存在した「家族の愛」や「共に過ごした時間」だけは、誰にも奪えない真実だったのだと思います。
『なりすまし』というタイトルは、ただの事件のトリックを示す言葉ではありません。
この作品が描いているのは、「他人にならざるをえなかった人たち」の姿です。登場人物たちは、皆、過去に深い傷を負い、自分という存在に絶望し「違う誰か」として生きることを選びました。彼らは嘘をついていたのではなく、生きるために「名を変える」しかなかったのです。
本作を通じて感じるのは、「本当の自分とは何か」という問いの重さです。名前や戸籍、過去や経歴がその人を決定づけるのであれば、偽名で生きた人生はすべて偽物だったのでしょうか。
浩次郎と妻・エリカ、そして娘・杏奈の三人が築いた日々は、名前が偽物だったからといって、意味を失うのでしょうか。
「どんな名前であっても、誰として生きていても、その人が本気で誰かを愛し、人生を懸命に歩んでいたのなら、それは間違いなく本物だ」と言われているようにも思いました。
浩次郎は、すべてを失いました。しかし、妻との日々、娘との時間は幻ではなかったはずです。彼の心には、確かに何かしらの温もりが残っていました。
それこそが、今回のなりすましの殻を脱ぎ捨てた彼が、初めて「自分」として立ち上がる力になったのです。
最後にひとつ、読者として考えたいことがあります。
それは、「過去を背負って生きる」ことと、「過去に囚われて生きる」ことは、まったく別物であるということです。浩次郎は、過去から逃れるために名前を変えました。けれど最終的には、自らの過去と向き合い、それでも生きる道を選びます。
私たちもまた、過去に傷つき、失敗し、後悔することがあるでしょう。でもそれを「なかったこと」にするのではなく、受け入れて、それでもなお自分の足で前へ進むことの大切さ。
その選択の大切さを、教えられたような気がします。
● 日本の戸籍制度の闇を知ることができた
● 事件の真相と真犯人に驚愕した
● 自分が本当に「自分」なのかを問いたくなる作品だった