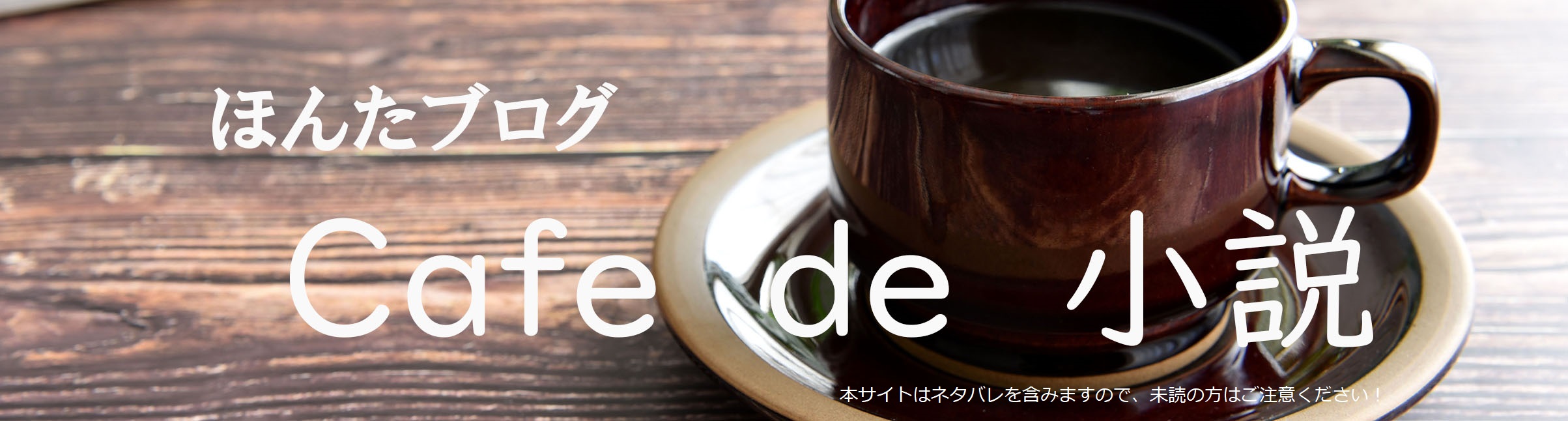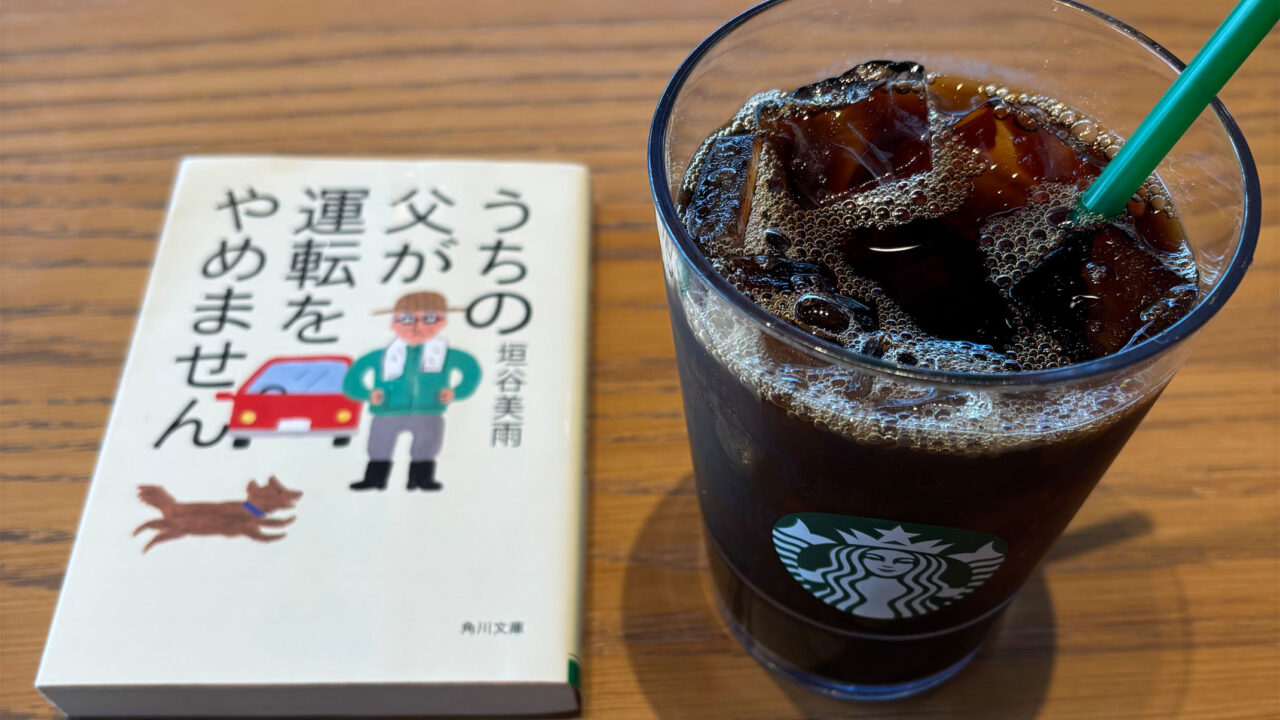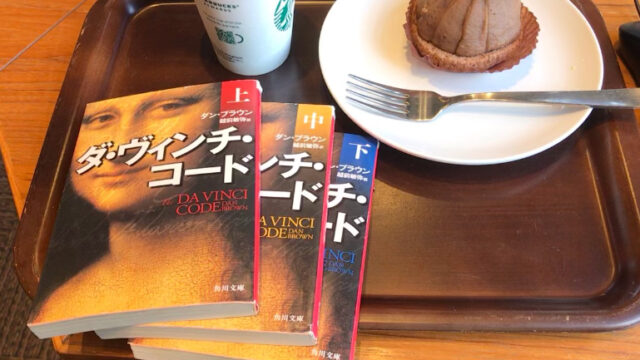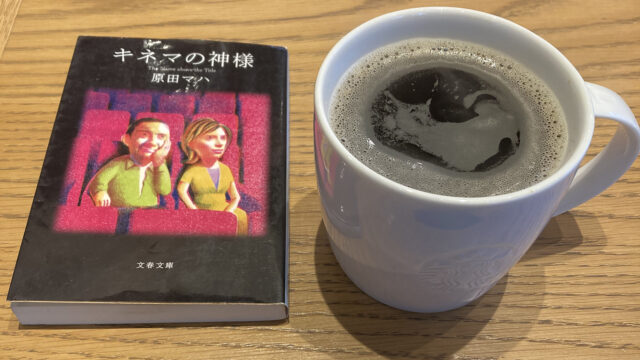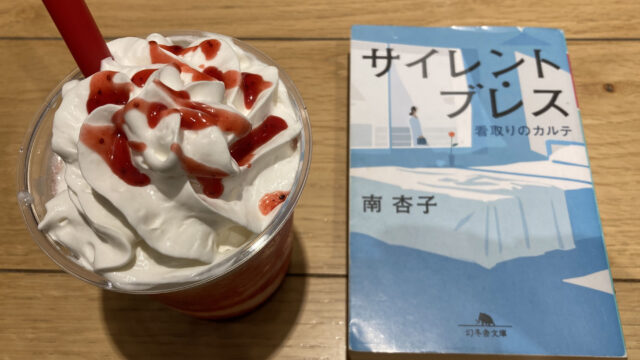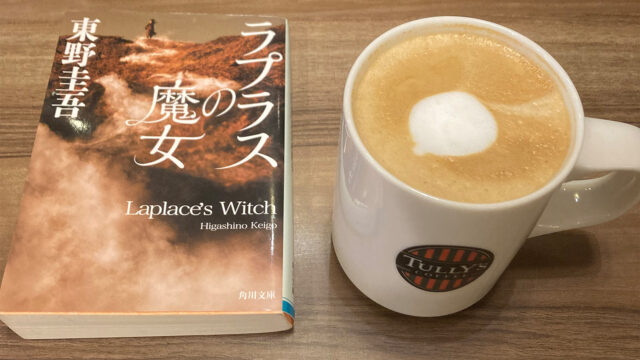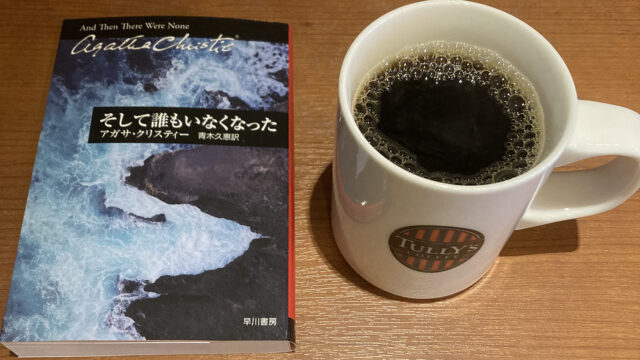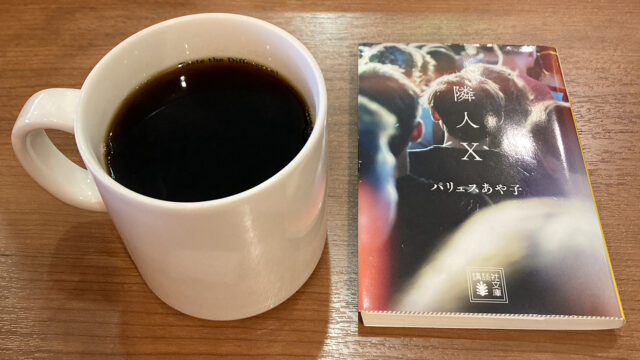私にとって、他人事とは思えない作品だと思い、購入しました。
実はうちの父親も運転をやめていません。母親を病院へ連れて行ったりするときにはどうしても車が必要になってしまうのです。
それが無ければ父親本人は「免許を返上する」とは言ってくれてます。でも、いつ何が起きるかわからないですよね。
本作品にはタイトルのように、ある男性の父親が絶対に「運転はやめない」と頑なに拒む、それをどうやって解決するのか、というストーリーになっています。
世の中にはこういった高齢者も多いのではないでしょうか。僕自身も年齢を重ねたら、同じように「自分は運転には自信があるから」と言って免許返上はしないかもしれませんし。
ただ、本作品にもメッセージがありました。そのメッセージを知るために、本作品を読んでみるのもよいかもしれません。
是非、読んでみてください!
目 次
1. こんな方にオススメ
2. 登場人物
3. 本作品 3つのポイント
3.1 頑固な父親への説得
3.2 息子の引きこもりと家族の葛藤
3.3 問題を解決する秘策とは
4. この作品で学べたこと
● 自分の父親が免許返上を頑なに拒んでいる方
● どうすれば運転をやめてくれるかを知りたい方
猪狩雅志は高齢ドライバー事故のニュースに目を向けた。78歳といえば親父と同じ歳だ。妻の歩美と話しているうちに心配になってきた。夏に息子の息吹と帰省した際、父親に運転をやめるよう説得を試みるが、あえなく不首尾に。通販の利用や都会暮らしのトライアル、様々な提案をするがいずれも失敗。そのうち、雅志自身も自分の将来が気になり出して……。父は運転をやめるのか。雅志の出した答えとは? 心温まる家族小説!
Booksデータベースより-
猪狩雅志・・・主人公。自分の父親が免許を返上しないことに悩む
雅志の父親・・頑固な雅志の父親。78歳という高齢
猪狩息吹・・・雅志の妻。サラリーマン生活を送る女性
猪狩息吹・・・雅志の息子。ひきこもりだが、田舎が大好き
1⃣ 頑固な父親への説得
2⃣ 息子の引きこもりと家族の葛藤
3⃣ 問題を解決する秘策とは
東京で暮らす50代の会社員、猪狩雅志。彼は、毎日のようにニュースで報じられる高齢ドライバーによる痛ましい事故のたびに、田舎で一人暮らしをしている78歳の父親の運転が気になって仕方ありません。しかし、「わしは死ぬまで運転する!」と頑として聞かない父親に、雅志は途方に暮れてしまいます。
この件を読んだだけで、自分の父を思い出します。僕の父はまだ理解があって「そろそろ、返上しようかな」と言ったりするのでまだマシかもしれません。本作品の雅志の父親はかなり手強そうです。
この作品が深く掘り下げているのは、高齢ドライバー問題の複雑性です。多くの場合、この問題は「危ないから免許を返納すべき」という単純な結論に結びつけられがちですが、作者はそうではないと提示します。
地方、特に過疎化が進む地域では、車がなければ生活が成り立たないという現実があります。スーパーは撤退し、バス路線は廃止され、病院も遠い。まさに過疎化の一歩をたどる町にとっては死活問題でしょう。
だから車はもはや贅沢品ではなく、日常生活を送るための「足」であり「命綱」なのではないでしょうか。父親が運転をやめられないのは、単なる意地やプライドだけではなく、生活そのものが脅かされることへの切実な不安があるからだと、雅志は徐々に理解していきます。
さらに、物語は雅志自身の人生にも深く切り込んでいきます。都会で忙殺される日々に疲れを感じ、妻との関係にも倦怠感が漂い、高校生の息子とは会話もままならない。中年期に差し掛かり、自身の生き方や家族とのあり方を見つめ直す雅志の葛藤が、父親の運転問題と並行して描かれます。
これは、現代社会を生きる多くの「子世代」が共感しうる、普遍的なテーマではないかと思うのです。親の老いや死と向き合う中で、自身の人生を見つめ直す、「親の介護世代」のリアリティが巧みに描かれているのです。
僕の両親も高齢になっていることを考えると、とても他人事ではないと考えさせられます。ただ運転をやめてほしい、というだけでなく、その周囲にある社会問題を突き付けられている気がするのです。この多層的な視点が、作品に深みと説得力をもたらしているのではないでしょうか。
物語が進む中で、主人公・猪狩雅志の抱える悩みは、父親の運転問題だけにとどまらず、自身の家庭にも暗い影を落とします。その中心にいるのが、高校生の息子・駿です。駿は、学校に行くのを拒み、自室に引きこもりがちになっていました。
雅志にとって、駿の引きこもりは、理解しがたい、そしてどう対処していいか分からない大きな問題でした。自身の仕事が忙しいこともあり、息子とのコミュニケーションは不足しが親子の間に深い溝ができていました。
妻もまた、駿の状況に心を痛めながらも、解決の糸口を見つけられずにいました。家庭内の空気は重く、雅志は父親の老いと息子の引きこもりという二つの大きな課題に板挟みになり、心身ともに疲弊していきます。
駿の引きこもりは、単なる「学校に行きたくない」という問題以上の、現代の若者が抱える閉塞感や未来への不安を象徴しているかのようでした。彼は都会の喧騒や競争社会に馴染めず、自分の居場所を見つけられずにいたのです。
雅志は、息子を叱咤したり、時には突き放したりもしますが、事態は好転しません。むしろ、親子間の距離は広がるばかりで、雅志は父親の運転問題と同様に、息子の問題にも無力感を覚えていました。
この時期の雅志は、自身の人生の停滞感と相まって、人生の袋小路に迷い込んだような状態にありました。
そんな中、雅志は父親の運転問題と向き合うため、定期的に田舎の故郷へ帰省するようになります。最初は渋々付き合っていた駿も、度重なる帰省の中で、少しずつ変化を見せ始めます。
田舎の自然、ゆったりとした時間の流れ、そして都会とは異なる人々の温かさに触れるうちに、駿の心は少しずつ解きほぐされていきます。都会では味わえなかった開放感や、肩肘張らずにいられる環境が、彼にとって新鮮だったのかもしれません。
祖父である雅志の父との交流も、彼にとっては良い刺激となります。都会では見せることのなかった表情や、ふとした瞬間に口にする言葉の中に、駿のわずかな変化が垣間見え始めます。
※ネタバレを含みますので,見たい方だけクリックしてください!
👈クリックするとネタバレ表示
主人公の雅志は、父親の運転を止めさせるために様々な手を尽くします。ネット通販の利用を勧めたり、都会での同居を提案したり、半ば強引に説得を試みたり。
しかし、どれもが父親の頑なな抵抗に合い、ことごとく失敗に終わります。この試行錯誤の過程が、多くの読者にとって「うちもそうだった」「わかる」という共感を呼びます。
八方塞がりの状況に陥った雅志は、ついに大きな決断を下します。それは、長年勤めてきた会社を辞め、東京での生活を清算し、父親の暮らす田舎に移住するというものでした。
そして、そこで始めたのが、なんと「移動スーパー」です。この展開は、単に父親の運転問題を解決するという目的に留まりません。移動スーパーというアイデアは、地方の買い物弱者、特に高齢者にとってはまさに「救世主」のような存在です。
車がなくても新鮮な食材や日用品が手に入るというサービスは、地域全体の高齢者の生活の質を向上させる可能性を秘めています。
この「移動スーパー」のアイデアは、現実への一筋の光を示すような解決策です。もちろん、現実には起業や地方移住には多大な困難が伴うでしょう。しかし、物語の中では、雅志が自身の人生を見つめ直し、社会貢献という新たな生きがいを見出す過程として描かれます。
この行動を通じて、雅志と父親の関係性も変化し、長年の溝が埋まっていく様子が心温まる筆致で描かれています。それは、単に問題解決だけでなく、家族の再生と個人の成長を描く物語へと昇華させているのです。
垣谷美雨さんは、これらの重層的な社会問題を、決して説教じみたトーンではなく、登場人物たちの葛藤や成長を通じて描くことで、読者に深く考えさせると同時に、どこか温かい気持ちを残します。
だからこそ、この作品は多くの人々に「自分ごと」として受け止められ、共感と感動を呼ぶ傑作となっているのです。
この小説が多くの読者から熱烈な支持を受けるのは、その多角的な視点と、読者が自身の経験と重ね合わせて深く共感できることあると言えるのではないでしょうか。
まず、高齢ドライバー問題は、まさに現代日本社会の重大な課題です。過疎化が進む地方では公共交通機関が衰退し、車が生活に不可欠なインフラとなっています。しかし、高齢化に伴う身体機能や認知機能の低下は避けられず、事故のリスクは高まります。
このジレンマを、家族の視点、そして高齢者自身の視点から丁寧に描き出しています。運転をやめることが、単なる「便利な移動手段を失うこと」ではなく、「生きがい」や「社会とのつながり」を失うことに直結しかねないという高齢者側の心情が、痛いほど伝わってきます。
次に、現代の家族像とその変遷も重要なテーマです。都会で働く子世代が、離れて暮らす親の老いや介護問題に直面する中で抱える葛藤、自身のキャリアと家族とのバランス、そして親子のコミュニケーションの難しさなどがリアルに描かれています。
雅志が父親と真正面から向き合う過程で、これまで見えていなかった父親の一面や、自身の人生に対する価値観の変化に気づかされる姿は、多くの読者にとって共感できることなのではないか。
そして、最終的に提示される「あるアイデア」。これは単なる個人の問題解決を超えて、地域社会のあり方や、新たなビジネスモデルの可能性にも言及しています。そういう発想の転換ができる作者の思考に感服しました。
社会が抱える課題に対し、個人がどのように向き合い、行動を起こし、そしてそれがどのように地域全体に波及していくかを考えることの大切さを学ばせられるのです。
● 自分の親にどう説得するかを考えることができた
● いろいろな問題を解決する本作品内の「あるアイデア」に感服した
● 物事は多角的な視点で考える必要があることを学んだ